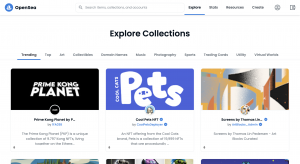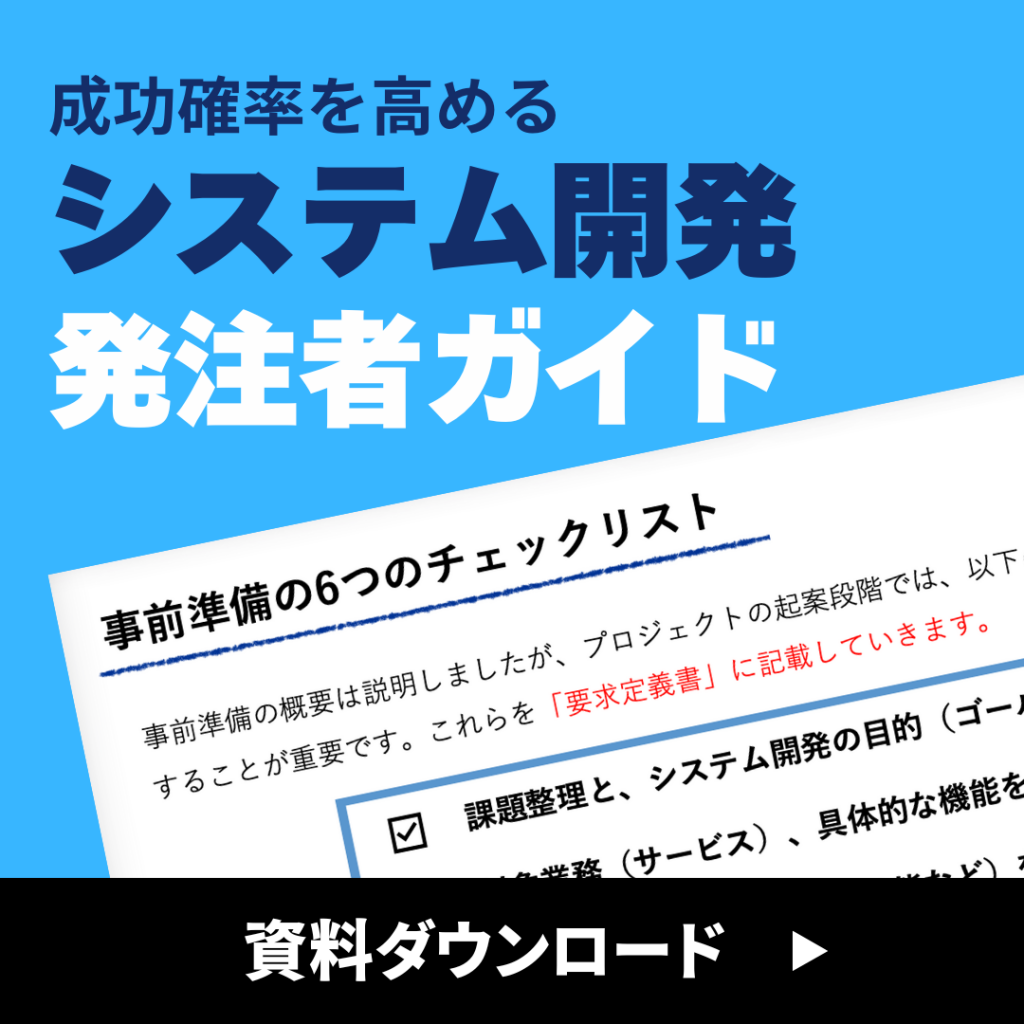「Web3(Web3.0とも呼ばれます)」という言葉が新たなバズワードとなっています。政府からも成長戦略として発表されるなど、よく耳にするけれどもその実体がよくわからない、なぜそんなに注目されるのか理由が分からないという人も多いのではないでしょうか。
Web3は一言で言うと、Web2.0の課題を解決する鍵となります。
本記事では、Webの歴史の変遷を説明した上で、現在のWeb2.0の問題点とその処方箋となりうるWeb3の世界について解説します。代表的なWeb3のサービスも紹介するので、より具体的なイメージを持ってWeb3を理解したい経営者やシステム担当者にとっておすすめの記事です。
Web3(Web3.0)とは | 中央集権から分散管理へ
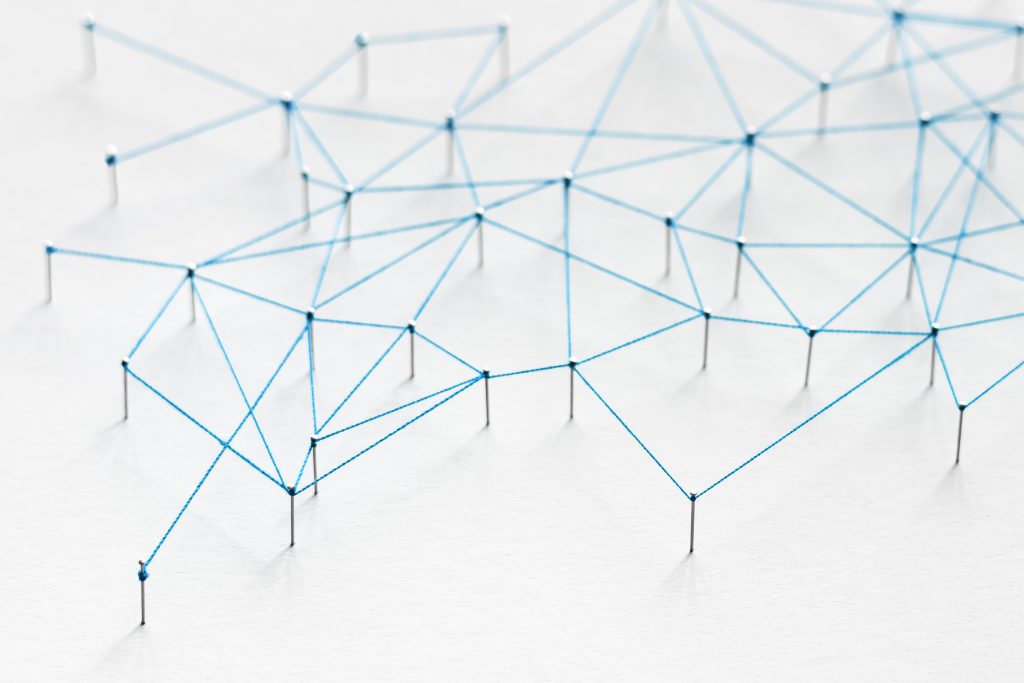
Web3とは一言で言うと「非中央集権のインターネット」のことを指します。
中央集権、非中央集権という言葉に馴染みがないので、イメージが湧きにくいかもしれません。私たちの現在利用しているインターネットは、Googleなどを中心とした巨大なプラットフォームがあることで、成り立っています。
Web3を知るためには、Web1.0に始まるインターネットの歴史を振り返る必要があります。インターネットの歴史の変遷を知ることで、より本質的にWeb3を理解しましょう。
| ・Web1.0:1989-2005年(ホームページの時代) |
| ・Web2.0:2005-現在(SNS・クラウド時代) |
| ・Web3.0:現在~ (ブロックチェーンの時代) |
Web1.0
Web1.0の時代は、WWW(=WorlsWideWeb)が普及し、個人がウェブサイトを作って情報を発信できるようになった時代です。一部のサイトを構築する技術を持った人を除いて、ほとんどの人がホームページのテキストサイトを「読む」時代でした。コンテンツはほぼすべて読み取り専用で、双方向性なやりとりはほとんどできないのが特徴です。
・1989-2005年
・ホームページ、受信、一方向性の時代
・読み取り専用ページの時代(読む時代)
・Read Only
Web2.0
Web2.0の時代は、ユーザーがより自由にインターネットを使用できるようになりました。情報の発信者と受信者が双方向なコミュニケーションをできるようになった時代です。Twitter、YouTube、Facabook、InstagramなどのSNSが普及し、誰もが気軽に発信者となり、画像や動画のシェアができるようになりました。
しかし、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)が台頭し、個人情報、個人の嗜好、行動履歴などのデータを独占する時代ともなりました。これらの問題点については後述します。
・2005-現在
・SNS・クラウド時代
・Read+Write
・双方向性、データ独占の時代
Web3(Web3.0)
Web3の時代はまだ明確な定義がありません。Web3を支える技術がブロックチェーンであるという点だけはっきりしています。
ブロックチェーンとは、取引情報が記録された台帳のことです。管理者が不在で、ユーザー全員がデータを共有し管理します。つまりWeb2.0の中央集権型から分散型へ移行し、個人がデータを所有する時代になるのです。
結果、特定の企業に依存せずとも個人がさまざまなデータにアクセスできます。Web2.0というGAFAMがデータを独占する時代から、新たな時代が幕を開けようとしています。
またネットワーク上の取引情報は常に暗号化されることから、セキュリティーのレベルが向上することも期待されています。
・ブロックチェーンの時代
・Read+write+Own
Web2.0の問題点
Web3はWeb2の問題を解決する鍵となります。改めてここではWeb2.0の問題点とはどういうものなのかを深堀してみましょう。
問題点1:中央集権
Web2.0の問題点1つ目は中央集権であるがゆえのセキュリティ問題です。現在は権力のある国や企業などがすべてをコントロールし、全ユーザーの行動履歴なども含めた個人情報がアプリケーションなどを通じて1か所に集まっています。それゆえ、懸念すべきはサイバー攻撃などのセキュリティリスクが非常に高い点です。
具体的には、2021年12月にLinePayで13万人の個人情報が漏洩しました。2019年にはFacebookで5億3000万人を超えるユーザーの個人情報が流出しました。
問題点2:プライバシーの侵害
Web2.0の問題点2つ目は、サービスの利便性と引き換えに発生するプライバシーの問題です。わたし達ユーザーはGAFAMを始め、さまざまな大企業に個人情報(住所、年齢、性別など)IDやパスワード、自身の嗜好、行動履歴などの情報を渡しています。
それだけではなく、Web上での行動も追跡されており、その結果として意思に反する広告が強制的に表示される場合があります。
問題点3:所有権の独占
Web2.0の問題点の3つ目は、ユーザーがクリエイトし発信するコンテンツにも関わらず、それらの所有権がユーザーではなく企業側にある点です。
たとえば、フォロワーが何万人もいるTwitterアカウントも、Twitter社にアカウントを凍結されたらコンテンツもフォロワーもすべて消えます。たとえば、トランプ元大統領のアカウントはTwitter社により凍結されています。
こういった事例は、わたし達が使用している情報やデータに実は自身の所有権がないことを如実に表しています。
なぜWeb3(Web3.0)が注目を集めるのか
ではここで改めてWeb3について考えてみましょう。Web3はいったいなぜ今注目を集めているのでしょうか。
結論から言うとWeb2.0の問題を解決できるからです。Web3はサービスを中央集権型から分散型(非中央集権型)へ変えていくことができます。多くの人に管理権限を分散させ、権限を集約させないことがWeb2の問題への処方箋となるでしょう。
では次は、非中央集権となることがわたし達にどういう恩恵をもたらすかを見ていきましょう。
プライバシーが守られる
Web2.0の時代のサービスは、ユーザーがさまざまな個人情報を登録という作業を通してGAFAMを始めとする大企業に渡すことで成り立っていました。無料で利用できるものがメインですが、その代わりに行動履歴なども提供していました。
最近ではCookie規制の動きが話題になっており、企業は自主的にユーザーのプライバシーを保護する動きをしているものの、まだまだGAFAMがユーザーの様々なデータを保有するという流れは大きく変わらないでしょう。
しかし、Web3のブロックチェーンを使用するサービスは、IDやパスワードの登録が不要です。各自がウォレットアドレス(アルファベットの数字の羅列)を持ち、その都度ウォレットのIDでログインできる仕組みです。匿名性が担保され、プライバシーが守られます。そこには個人情報漏洩という概念自体がありません。
つまり、Web3.0の時代では、自らがデータを管理できるのです。Web3の具体的なサービスは後述します。
国や企業に規制されなくなる
Web3の時代の大きなメリットは、個人間の送金ができるようになる点です。現在は銀行などの金融業者を介して送金やお金の貸し借りをしています。仲介の金融機関に個人情報を登録し、少なからず手数料を取られています。
しかしWeb3の時代になると銀行口座をもたない人にもお金を送れるようになります。世界中どこにいる人にでもウォレットさえあれば瞬時にお金を送れるようになるのです。
現在は中央集権的なサーバーが存在し、それがダウンすると障害が発生してサービスを利用できなくなりハッキングのリスクもありますが、Web3ではそういった懸念から解放されます。また現在、一部の国ではそうしたサーバーに厳しい規制・検閲があり、特定のサービスが利用できない例も見られます(中国におけるGoogleなど)。Web3の世界ではそうした国からの規制からも開放されると期待されます。
クリエイターエコノミーの発展
Web2.0ではGAFAMを始めとするプラットフォーム企業に主導権があります。たとえば、クリエイターがTwitterやYouTubeでフォロワーを増やしても、間にいる企業がそのサービスを停止してしまったら、クリエイターとフォロワーの繋がりはなくなってしまいます。プラットフォーマー主導で経済がまわっている状態と言えるでしょう。
しかしWeb3.0では「クリエイターエコノミー」というクリエイターが中心の経済圏が活発になります。クリエイターがファンから直接お金を稼ぐことのできる仕組みがまわり始めるのです。
たとえば、クリエイターとファンが直接コミュニティでチャットを通じて繋がるDiscord、クリエイターが直接ファンに届けるニュースレターサービスのSubstackなどです。ファンと直接つながった後のマネタイズの方法として、NFTアートも流行しています。NFTとは、NFTは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略で、自分の作品を唯一無二のデジタル資産にできる仕組みです。
代表的なWeb3(Web3.0)のサービス
Brave
BraveはWeb3.0世代のウェブブラウザとして注目されているブラウザです。プライバシー保護に特化しており「Brave Shield(ブレイブシールド)」という個人データを収集する広告をブロックする機能があります。
通常のブラウザだと1度商品を閲覧すると、その後繰り返しそれに関する広告が表示されますが、Braveではそういったことがありません。
また、広告を閲覧するとBasic Attention Token(BAT)という仮想通貨を獲得できる「Brave Rewards(ブレイブリワーズ)」という機能も非常に画期的です。
OpenSea
OpenSeaとはNFTコンテンツの販売・購入・二次流通(転売)が可能なマーケットプレイス、いわゆるECサイトです。OpenSeaではアートを始め、写真、音楽などさまざまなNFT作品が個人間で売買されています。従来のマーケットプレイスの違いはユーザー登録の必要がなく、ウォレットを連携させるだけで作品を購入できる点です。もちろん決済情報も必要ありません。
また、出品したクリエイターの作品は二次流通でユーザー同士が売買しても、発行者へ永続的にロイヤリティを還元できるのも特徴です。
こうしたNFTコンテンツにつては、メタバース上で発表したり販売したりすること相性がよく、今後、関連サービスも増えていくことが予想されています。
まとめ
本記事ではWebの変遷からWeb2.0の問題点、それを解決する鍵としてのWeb3の可能性について紹介しました。主にWeb3の魅力について触れましたが、課題もあります。
たとえば、Web3サービスを使いこなすにはITリテラシーと仮想通貨に関する知識が必要です。時に高いスキルが必要となりますが、先述の通りWeb3は非中央集権であるがゆえに企業のサポートはなくすべて自己責任となります。
しかし時代は確実にWeb3の時代となりつつあり、少し先になるかもしれませんが、社会の形は大きく変わろうとしています。なるべく早いうちから、分散型のサービスを利用して、来るべき本格的Web3の時代に備えることが必要となるでしょう。