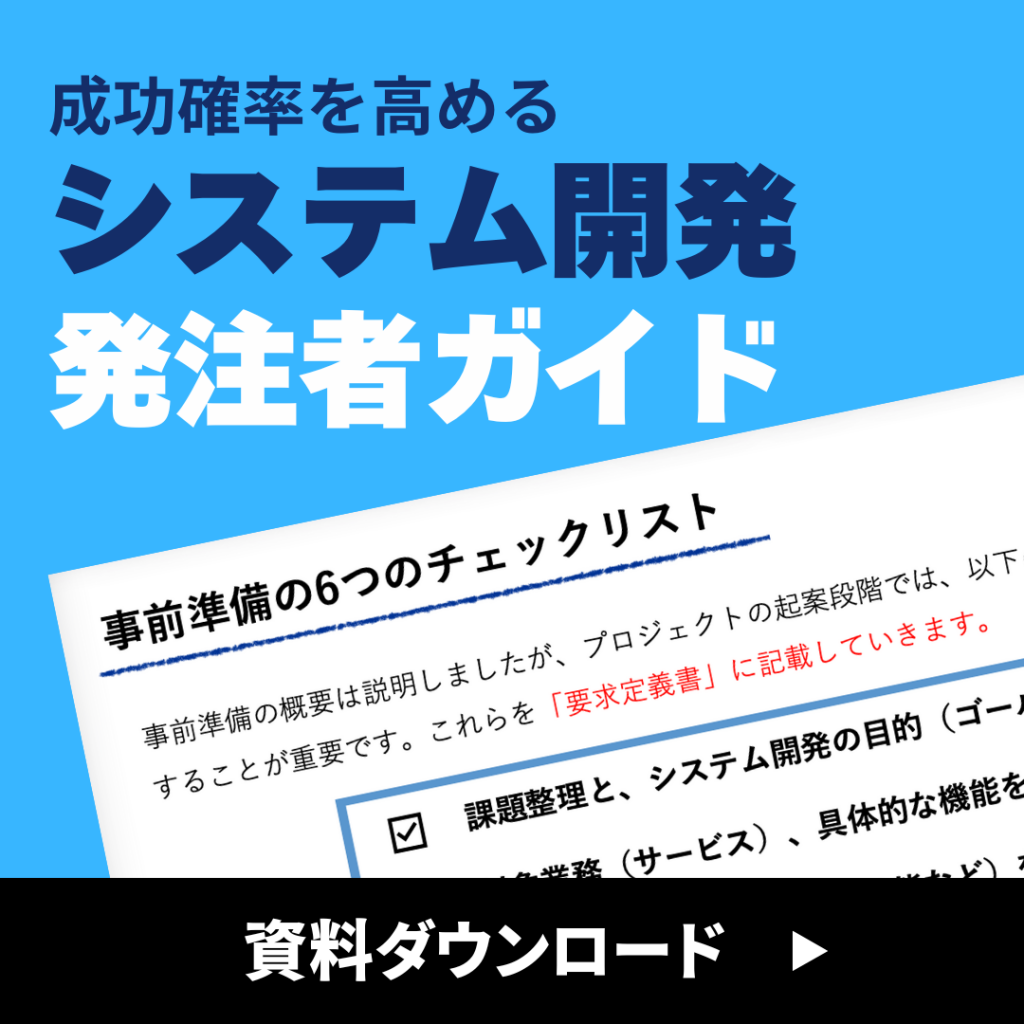新型コロナウイルスによる感染症のまん延により、顧客がECサイトなどオンラインを活用する機会が以前より格段に増えています。企業は実店舗などオフラインと、ECサイトなどオンラインの双方で顧客満足度を向上させていくことが重要です。
オムニチャネルやOMOといった新たなマーケティング概念も誕生しており、オンラインとオフラインの垣根が無くなりつつあると言えるでしょう。
本記事では混同しやすいオムニチャネルとOMOの違いについて分かりやすく解説します。
<目次>
オムニチャネルとOMOの違い
・オンラインとオフラインの区別の違い
・視点の違い
オムニチャネルやOMOを進めるメリット
・顧客満足度の向上
・販売機会を逃さない
オムニチャネルとは?
オムニチャネル(Omni-Channel)は小売業を中心に広がりを見せつつあるマーケティング戦略です。
オムニ(Omni)はありとあらゆるという意味で、チャネル(Channel)は販売経路を表します。つまり、オムニチャネルはオフラインである実店舗、オンライン上のECサイトなどあらゆる顧客との接点でのマーケティング戦略だと言えるでしょう。
メルマガやテレアポ、SNS、スマホのアプリなどの顧客接点もチャネルのひとつです。さらには本屋とカフェの融合など、業界を超えたチャネルも統合するのもオムニチャネルの融合だと言えます。
オムニチャネル戦略では実店舗やECサイトなどのデータを統合することによって、オンラインとオフラインでシームレスな顧客体験(UX)を提供可能です。オンラインとオフラインの双方で顧客へ価値を提供できるため、販売機会を逃さないためのマーケティング戦略だと言えるでしょう。
日本ではセブンイレブンで有名なセブン&アイグループが展開する「オムニ7」が有名です。

オムニ7を利用すると、全国18,000店のセブンイレブンで、イトーヨーカドーやロフト、アカチャンホンポといったセブン&アイグループの製品を受け取りすることができます。実店舗が遠方にしかない場合でも、セブンイレブンで受け取りができることによって、顧客の購買意欲を刺激することが可能なサービスです。
OMOとは?
OMOはOnline Merges with Offlineの略語で、元Googleチャイナの李開復(カイフ・リー)氏が提唱したオンラインとオフラインの融合を意味するマーケティング戦略です。OMOとはオンラインとオフラインを区別することなく連携することで、顧客にとって利便性の高いサービスを提供する戦略と言えるでしょう。
OMOと似た概念にO2Oがあります。
O2Oはオンラインで情報発信を行ない、オフラインのサービスに顧客を誘導する戦略です。OMOのようにオンラインとオフラインを行き来する概念ではないので、覚えおきましょう。スマート家電やキャッシュレス決済が普及したことで、オンラインとオフラインの垣根は顧客にとってあってないようなものになりつつあります。
顧客がオンラインやオフラインを意識せずにサービスを受けられるように、企業もOMOを試行錯誤しているのです。
OMOの例としては、マクドナルドやスターバックスの「モバイルオーダー」が挙げられます。
事前に店舗で受け取る商品をスマホ上で注文し、PayPayなどキャッシュレス決済を行なうと、店舗では商品を受け取るだけで良いというサービスです。店舗スタッフとオーダーや金銭のやり取りがなく、スムーズに商品を受け取ることができるため、コロナ禍で普及が加速度的に進んでいると言えるでしょう。
オムニチャネルとOMOの違い
オムニチャネルとOMOは、どちらもオンラインとオフライン双方での顧客接点に関するマーケティング戦略です。
混同しやすい概念ですが、違いはどこにあるのか確認してみましょう。
オンラインとオフラインの区別の違い
オムニチャネルはありとあらゆるチャネルという意味ですが、オンラインのチャネルとオフラインのチャネルは明確に区別されています。それぞれのチャネルの顧客データなどは統合されますが、チャネル自体は独立していると考えると分かりやすいでしょう。
一方のOMOでは、オンラインとオフラインを融合させるマーケティング戦略のため、区別されていないことが特徴です。
オンラインとオフラインの区別をしているかどうかという点で、オムニチャネルとOMOには違いがあります。
視点の違い
オムニチャネルとOMOは「視点が違う」ということも覚えておきましょう。
オムニチャネルは企業側視点での戦略です。企業が持つチャネルをどのようにして連携させるかを考えることによって、顧客満足度を向上させようとします。
一方のOMOは顧客視点での戦略です。スマホやキャッシュレス決済を活用して、いかに顧客に上質な体験をしてもらうかを考えるマーケティング戦略だと言えるでしょう。
また、オムニチャネルやOMOは、DXの具体的戦略とも言えますので、ぜひ推進していきたいものです。
関連記事 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?成功する為の5ステップと事例紹介
オムニチャネルやOMOを進めるメリット
スマホやキャッシュレス決済が当たり前になった今日において、企業はオンラインとオフラインの双方で顧客満足度を上げていく必要があります。
オムニチャネルやOMOを推進するメリットを確認していきましょう。
顧客満足度の向上
日本は「おもてなし」の精神でも知られるとおり、オフラインの実店舗などでサービス品質が高いことが特徴です。
オムニチャネルやOMOなどオンラインを巻き込んだマーケティング戦略を展開することで、より高い顧客満足度を得ることができるようになるでしょう。
オンラインとオフラインの顧客データを統合するオムニチャネル戦略においては、データの分析により、顧客に対してより細やかなサービスを提供できる可能性があります。データに基づくマーケティングは、まさにあらゆる企業が推進するDXに通じる戦略です。
関連記事 DXでカスタマーエクスペリエンス(CX)を向上 | 成功企業事例の紹介
販売機会を逃さない
オムニチャネルやOMOを推進することで、オンラインとオフライン双方で顧客との接点を持つことができます。
顧客との接点が増えれば増えるほど、販売機会が増加するため、機会損失を抑えることが可能です。さらにオンラインとオフラインで、顧客データや販売データを統合するので、適切な在庫数をリアルタイムで把握することもできるでしょう。
データに基づくDXにより、オムニチャネルとOMOは成功する確率が高まります。
今後のオムニチャネルやOMOのトレンド
新型コロナウイルス感染症のまん延により、顧客の生活様式は一変しました。
今後もオムニチャネルやOMO推進に代表されるオンラインの活用は、どの企業もこぞって取り組んでいくでしょう。
今後のトレンドについて確認していきます。
市場は拡大する
各企業がDXやデータドリブンマーケティングに力を入れています。
今後、デジタル技術とデータ活用を中心としたDX推進で遅れを取る企業は淘汰されていくでしょう。
DX推進と通じるところがあるオムニチャネルやOMOの市場は、今後も拡大していくことが確実です。
キャッシュレス決済が浸透したように、オムニチャネルやOMOが新たなスタンダードになる日も近いと言えるでしょう。
また、オムニチャネルやOMOを取り入れる為のテクノロージも進化しています。CDPはその代表で、様々なチャネルに分散した顧客情報を一元化し、より良い顧客体験の設計に欠かせない技術となりました。
関連記事 データドリブンとは何か?DXにも欠かせないデータ分析の必要性
新たなサービスが生まれる
マクドナルドやスターバックスなどで導入されたモバイルオーダーのように、オンラインとオフラインを融合した新たなサービスが、今後どんどん出てくる可能性があります。日本全国にホームセンターを展開するカインズが、アプリのリリースやスマホで注文した商品を店舗で受け取ることができるサービスを始めたりと、デジタル化に舵を切ることは10年前誰が想像できたでしょうか。
それと同時に、顧客が一度オムニチャネルやOMOで良い顧客体験を経験すると、そうでないサービスにおいて不満やストレスを感じるでしょう。つまり、今まで以上に満足度に差がついてしまうことが予想されます。
まとめ
オムニチャネルやOMOは、スマホが普及してオンラインとオフラインの境界線が無くなりつつある今日において、重要なマーケティング戦略です。各企業で推進しているDX戦略とも通じるところがあり、今後あらゆるチャネルで顧客満足度を上げていくためにも、オムニチャネルやOMOに力を入れていく必要があるでしょう。