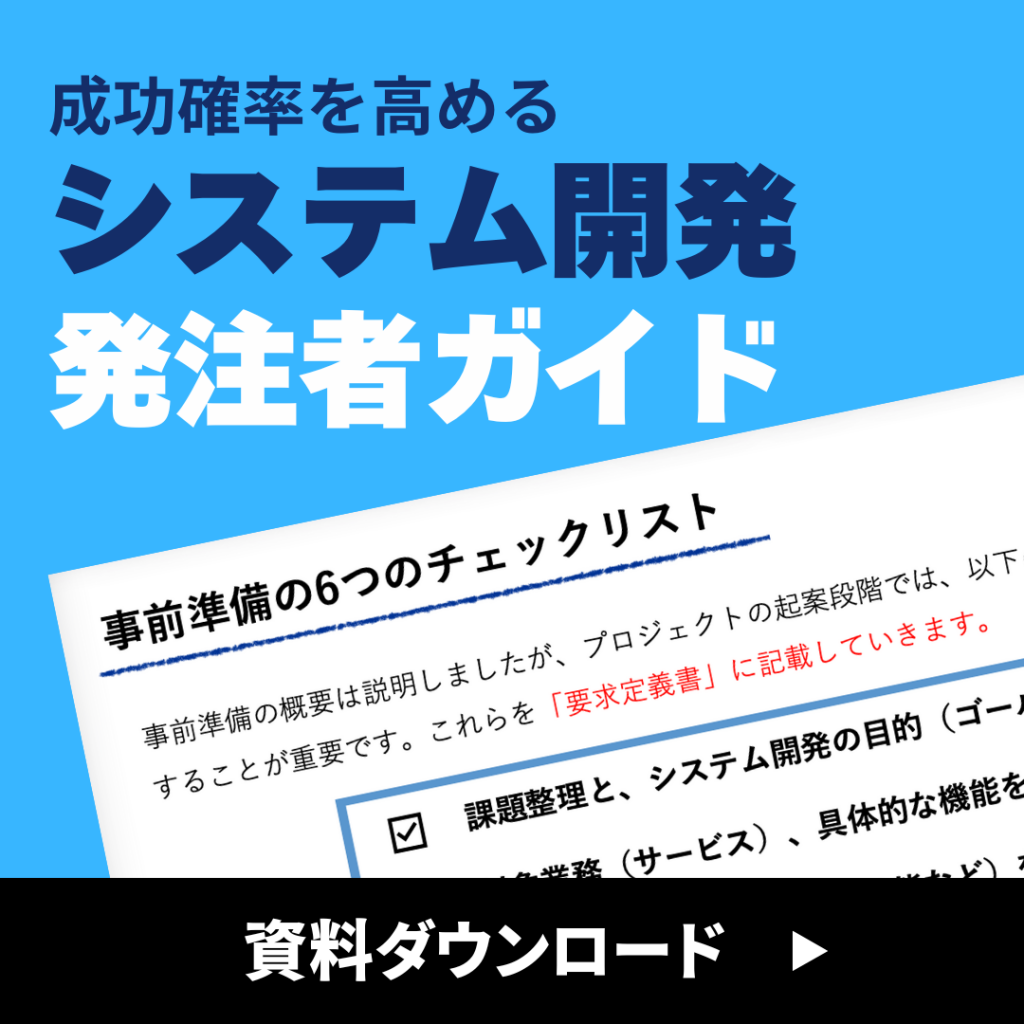ローカル5Gというワードは浸透したものの、具体的な事例や、どのように活用すれば良いかが分からない方が多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はローカル5Gの概要説明から歴史、具体的事例を交えながら、どのようにすればローカル5Gを活用してDXを成功させることができるのかを解説します。
ローカル5Gとは??

ローカル5Gとは企業や自治体が、エリアや建物内に専用の5Gネットワークを構築することを言います。
通常の5G電波は各通信事業者から提供されており、未だに全国をカバーできていない状況です。しかしローカル5Gであれば、まだ5Gエリアでない自社内のエリアや建物内にも5Gネットワークを構築することが可能となります
ローカル5Gの歴史
これまで、モバイル通信は「2G」「3G」「4G・LTE」と進化してきました。
より高速に大容量のデータを送受信することができるようになり、スマートフォンや動画の普及に繋がりました。
この4Gを更に進化させたのが「5G」です。
日本では2020年に商用が始まり、より高速で大容量の通信はもちろん、「低遅延」「多接続」という特徴も兼ね備えています。
そのなかでも「ローカル5G」は通信事業者に依存せずに5Gネットワークの構築を行う方法として総務省が提唱・普及をすすめています。
ローカル5Gメリット
ここでは、ローカル5Gのメリットを4点ご紹介します。
・Wi-Fiよりも広範囲かつ高速なネットワーク
これまで、局所的なネットワークの構築にはWi-Fiが使われてきました。
ローカル5GではWi-Fiに比べて広範囲に電波を飛ばすことができます。
その上、通信速度も速いため、より安定した通信環境を構築することが可能です。
・通信トラブルを受けづらい
ローカル5Gは独立したネットワークのため、災害時など通信が多く発生するタイミングで、キャリアの通信が不安定になることなどの影響を受けづらいです。
なにかトラブルが合ったとしても自前で修復が可能なため、安定したネットワーク環境を維持することができます。
・キャリアに左右されない
通信事業者の提供する5Gでは、まだまだ5Gの通信がカバーできていないエリアも多くあります。また、キャリアのさじ加減によって通信が不安定になることもしばしばありますが、ローカル5Gであれば独自のネットワークのためこれらの影響を受けません。
・セキュリティ強度が高い
ローカル5Gは独自の切り離された通信網であり、電波の特性からも通信が傍受されにくいという特徴を持っています。
そのため、Wi-Fiに比べてもセキュリティ強度が高いと言えます。
ローカル5Gのデメリット
次に、ローカル5Gのデメリットを4点ご紹介します。
・遮蔽物に弱い
ローカル5Gでは、ミリ波と呼ばれる直進性の高い電波を使います。
そのため、遮蔽物があると通信が遮断されやすいという特徴があります。
遮蔽物の多い環境の場合は注意が必要です。
・免許取得が必要
ローカル5Gは国の定める要件を満たしたうえで免許取得が必要です。
土地の所有権やその土地に基地局を設置するための申請と言った作業が必要になります。
手数料もかかる上、免許取得までには2ヶ月程度かかると言われています。
・導入費用
基地局を建てる必要があるため、システムによっては大規模な工事が必要になります。
範囲や要件によっては数千万円以上かかる場合もあると言われています。
・コストの不透明さ
5G自体が2020年に商用開始したばかりということもあって、導入費用や維持費がどれくらいかかるかが不透明です。唯一わかっているのは電波法で定められている電波利用料です。
【設備 電波利用料】
ローカル5G基地局 年額2,600円/局
ローカル5G陸上移動局 年額370円/局
自営等BWA基地局 年額19,000円/局
自営等BWA陸上移動局 年額370円/局
ローカル5Gの活用事例とその効果について

海外事例
・事例① ブラジルの大豆農家による収穫量拡大のための5G技術の活用
ブラジルの大豆農場において、生産増大や病害の対策にファーウェイの5Gの技術を活用する試験プロジェクトを行った事例です。
畑に設置したセンサーや刈取機、ドローンからデータを収集して収穫量の改善に役立てます。
広大な農地をカバーするためにローカル5Gの広域な通信網を利用しています。
・事例② コネチカット大学でのローカル5Gネットワーク構築(AT&T)
アメリカのコネチカット大学におけるローカル5Gネットワーク構築の事例です。
通信事業者のAT&Tが、ミリ波を使ったローカル5Gネットワークを構築し、データサイエンス関連の取り組みやテックインキュベーションプログラムなどの支援に活用される想定です。
より高速かつ低遅延な通信でアプリケーションにアクセスできるようになり、ネットワークは完全プライベートであるためリモートでのアクセスも可能です。
・事例③ 工場ネットワークの柔軟化(John Deere)
アメリカの農業機械メーカーであるJohn Deere社のローカル5Gを利用した生産ラインの設計を行う事例です。
同社の生産ラインでは、有線によるネットワーク接続を行っている設備が多数利用されており、これらの設備の無線化を行うことで、製品による生産ラインの変更などをより迅速にかつ簡単に行えるようにすることを目的としています。これまで、通信の安定性や速度の問題から有線でのネットワーク接続としていましたが、5Gのおかげで無線化できる目処が立っています。
国内事例
・事例① ローカル5Gを利用したカキ養殖の生産性向上
NECネッツアイ株式会社による、海中の状況をリアルタイムで把握することで、海面養殖における生産性の向上を目指した事例です。
遠隔地から水中ドローンを遠隔操作することで、海中の状況を「映像」と「センサーから得られた環境データ」により把握することで生産性を向上させることができます。
5Gの特徴である、超大容量通信をつかうことで、海中の状況を高精細な映像で把握することができるため、より正確に海中の状況を把握することができるようになっています。
Wi-Fiでは、通信範囲が狭く、速度も足りないため、陸地からの遠隔操作と映像監視は難しいとされていましたが、ローカル5Gを使うことでより効果的に海中の状況を遠隔地から把握することができるようになっています。
・事例② 農機の遠隔監視制御による自動運転等の実現
東日本電信電話株式会社による、複数台のトラクターを遠隔地から監視制御することで、自動運転を実現した事例です。
ローカル5Gとキャリアの5Gを上手く使い分けることで、農地と農地の間も自動でトラクターを運転させています。5Gの特徴である、超低遅延な通信と多接続により複数のトラクターを安全に制御することができています。
農業従事者は夏場の猛暑日などでも、自宅等から遠隔で状況を把握することができます。
また、新規就農者の減少による労働力不足や高齢化による収益力低下といった課題の解決に効果を発揮しています。
・事例③ 工場内の目視検査や品質管理の遠隔化
住友商事株式会社による、製品の目視による外観検査において、8Kの超高精細カメラで撮影した映像とAIを用いて自動で傷等を検知する事例です。
5Gの特徴である超大容量、超高速通信を活用しています。
これまでのWi-Fi等を用いた通信では扱えないような大容量の通信を、高速に処理することができるため、非常に大きな効果を生み出していると言えます。
これにより、わざわざ工場に出向かずとも検査員はAIの結果と映像のチェックを行うだけで検査を済ませることができるようになります。
ローカル5G活用のために乗り越えるべき課題
・技術理解の難しさ
5G自体が2020年に商用化が開始されたばかりということもあり、技術的な理解が難しいという課題があります。
無線通信は目に見えないため、アンテナの角度やちょっとした位置によって安定性に大きな影響を与えます。こういったノウハウは、専門業者にしか持ち得ないため、ブラックボックス化しやすいです。また、ローカル5Gの活用が期待されているIoT分野は、ソフトウェア、ハードウェア、通信の複合技術の集まりであるため、非常に難しい分野であると言われています。
・免許申請
先述の通り、ローカル5Gを活用するためには免許を取得する必要があります。
電波法に沿って、電波を発するデバイス等を使う際には許可が必要なのです。
具体的には、電波状況の確認・証明や無線設備の性能の確認、電波干渉の確認などが挙げられます。
無線の免許は資料を提出して終わりということではなく、各地の総合通信局や総務省に訪問し、書類の説明や質疑応答の対応を行います。
無線の利用に慣れていないと、このあたりの申請のハードルは高いと言えるでしょう。
・ソフトウェアの理解
ローカル5Gの活用のためには、これまでとは違うソフトウェアに対する理解も必要です。
・機器コストの問題
ローカル5Gの課題として、機器コストが高いことも挙げられます。
NECや富士通といったベンダー各社は詳細価格こそ公表はしていませんが、導入費用でおおよそ数千万から1億円弱かかると言っています。
これはローカル5Gの環境構築にかかるコストであり、ローカル5Gを活用するための各種デバイスの費用がさらにかかってきます。
5G対応のモジュールやデバイスはまだまだ価格が高いので、そういった機器コストをどのように抑えていくかが今後の課題となりそうです。
・設置コストや維持コストの不明確さ
ローカル5Gはまだまだ始まったばかりであり、デメリットでもお話したようにコストが不透明です。設置コストもどれくらいかかるか見積もりが難しく、維持にかかるコストとして電波利用料以外にはっきりとわかっているものはありません。
大手ベンダーに頼むと、数千万規模の予算が必要だと言われていますが、具体的にどこにどんな費用がかかるかは明らかになっていません。
導入をすすめるにあたって、大きな課題となりそうなのが、このコスト感の不透明さでしょうか。
5G案件を相談できる国内SIベンダー
■富士通株式会社
富士通は、総合ITベンダーでIT系の様々なサービスを企業向けに提供しています。
ローカル5Gの導入はもちろんのこと、これまでの事業で培ってきたノウハウを活かした「ローカル5Gソリューション」を提供しています。
■NEC
日本電気株式会社は、官公庁や企業向けにITソリューションを提供する電機メーカーです。
ローカル5Gでは、導入からシステム設計・構築、その先の保守までトータルサポートするサービスを展開しています。
また、オープンイノベーションを起こす場として、ローカル5Gラボやコミュニティの運営なども行っています。
■CAMI&Co.
株式会社CAMI&Co.は、IoTを活用した技術に関してコンサルティングから開発までを行っている企業です。
特に理解の難しいIoT技術に関して、ハードウェアからソフトウェア、通信まで相談が可能です。ハードウェアもソフトウェアも自社で完結できる数少ない企業です。
■日立システムズ
株式会社日立システムズは日立グループのIT分野の中核を担うシステムインテグレーターです。
ローカル5Gに関しては、ワンストップ・ソリューションのラインアップとして、事前に免許不要の電波で検証等を行い、適切な無線通信システムン設計や構築を支援する「ローカル5Gアセスメントサービス」を展開しています。
メーカー系では業界最大手のSIerであり、システムの構築だけでなく、運用や保守にも強みを持っています。
■テックファーム
テックファーム株式会社は、コンサルティング・設計開発から保守運用までをワンストップで提供する独立系のSIベンダーです。様々な企業と5Gに関する実証実験を行うなど、5Gに関する知見が蓄積されています。また、センサーを使った業務車両の動態管理など、IoT分野での実績が多いのも特徴です。
まとめ
ローカル5Gについて、事例を交えて解説してきました。
まだまだ新しい技術であり、言葉だけが先行している分野ですが、国内外ですでに様々な事例で活用が進められています。
従来のWi-Fiネットワークに比べて、通信範囲が広く、通信速度や通信容量も大きいため、これまでネットワーク化が難しかったような場所や分野でも活用が可能です。
導入コストや運用コストは不透明なところは多いですが、今回ご紹介したようなベンダーに問い合わせることで、コスト感も確かめられるでしょう。