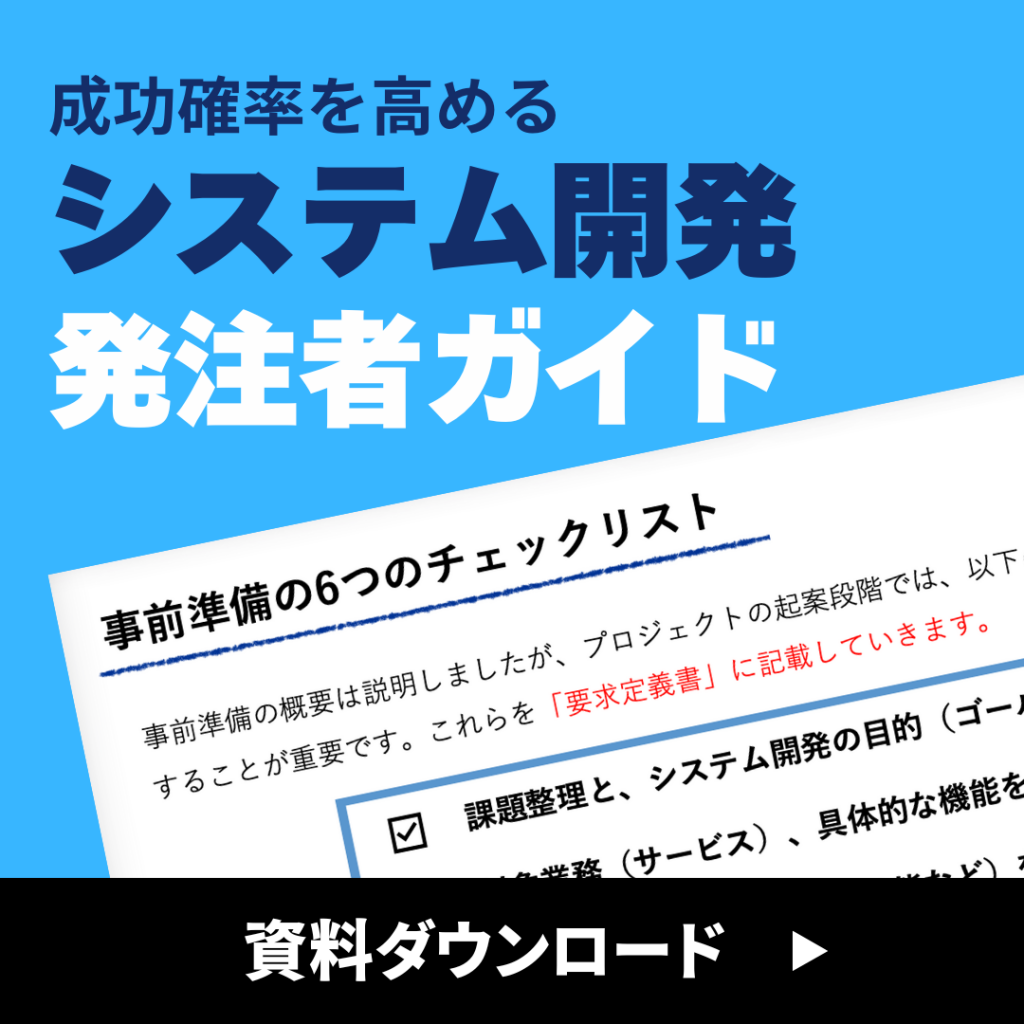近年、人気商品やイベントチケットの転売問題が深刻化しています。特定商品の大量購入による価格の高騰や、一般消費者への購買機会損失は、企業にとってブランド毀損やファン離れにもつながりかねません。
こうした課題に対し、AI技術を活用した転売対策に注目が集まっています。
本記事では、「転売 x AI」をテーマに、近年増加する不正購入の傾向を概観しながら、企業による最新の転売対策事例を紹介します。
また、CAPTCHA連携やアクセス制御、本人認証強化など、AIを用いた具体的な手法についても解説し、転売対策を検討中の企業担当者にとって、実務に活かせる視点をお届けします。
<目次>
「転売対策」が注目されている3つの理由
・転売によって公平な顧客の購入機会が奪わる
・転売によってブランドイメージが低下する
・オンライン上での転売被害が拡大
転売防止事例5選
・メルカリの政府備蓄米転売禁止AIシステム
・カメラのキタムラのAI転売対策
・チケット転売対策にAIを活用
・サイン入りグッズの画像判定で転売対策
・健康食品ECサイトの転売対策
「転売対策」が注目されている3つの理由
転売が社会問題化している昨今ですが、どうして大きな問題になっているのでしょうか。主な理由として考えられるのは、次の3つです。
- 公平な顧客の購入機会が奪わる
- ブランドイメージが低下する
- オンライン上での転売被害が拡大
転売の問題は個人間だけでなく、企業イメージにも大きく影響を及ぼします。また、近年はオンライン上で多くの手続きができるようになり、便利な反面犯罪に利用されることも少なくありません。転売も犯罪や不正の温床となっているのが現状です。
上記の3点について、もう少し詳しく解説しましょう。
転売によって公平な顧客の購入機会が奪わる
転売による問題として記憶に新しいニュースが、「コメの転売」やマクドナルドのハッピーセット「ちいかわグッズ」です。SNSでは「商品が無い」「買い占められている」などの書き込みが散見されていました。
買い占められた商品はインターネット上で、定価よりも高い価格をつけて転売されます。
このように、転売によって一般消費者が手に入れられなくなるだけでなく、定価で買えない事態が発生します。純粋にその商品を購入したいと考える人やファンにとっては、非常に残念なニュースです。
また、転売への不満は転売している人だけでなく、転売対策を実施しない企業側に不満が高まってきました。したがって転売の発生により、企業への信頼が損なわれる事態にもつながります。
転売によってブランドイメージが低下する
転売対策を実施しないブランド側に不満が高まりイメージが低下するだけではありません。転売品に対する品質保証やアフターサービスの有無が問題視されています。
転売品は保証されない可能性があり、不具合が発生した場合には消費者が不利益を被らなければなりません。商品が保証されないとなると、さらにブランドイメージの低下につながるでしょう。
したがって企業側は、ブランドイメージを守るために何らかの対策を講じなければならず、多くの労力が必要とされます。
オンライン上での転売被害が拡大
近年、インターネットが発達したことやコロナ禍でネットショッピングが手軽に利用できるようになったことなどにより、ネットショッピングの利用率が高まっています。
また、ネットショッピングの利用率が高まると同時に、オンライン上での転売被害が拡大しているのが現状です。
転売被害に対して、ネットショッピングッピングの関連企業は、不正購入や転売を防ぐためのシステム導入や対策が求められるようになりました。
AIを活用した転売防止ソリューション5選
転売の問題が大きくなるにつれ、企業側に転売対策が求められています。近年、注目を集めているのが、AIを活用した転売防止ソリューションです。
AIを活用した転売防止ソリューションにはさまざまな方法がありますが、主な種類と仕組みを下表にまとめました。
| ソリューション種別 | 仕組みの概要 | 主な活用分野 |
| 購入行動・異常検知型AI | 購入履歴・行動パターンをAIが分析し、異常な注文や転売目的の取引を自動検出。 | ECサイト、家電、限定商品 |
| 顔認証・生体認証型AI | チケットや入場時に顔認証を行い、本人以外の利用や譲渡を防止。 | イベント、ライブ、スポーツ |
| 画像認識型AI | サインや特徴を画像からAIが判別し、転売サイトでの出品を自動検出。 | サイン入りグッズ、限定品 |
| ボット検知・アクセス監視型AI | ボットや異常アクセスをAIがリアルタイムで検知し、購入をブロック。 | 人気商品、チケット販売 |
| ブロックチェーン・NFT型 | NFTやブロックチェーンで所有者情報を一元管理し、不正な転売・譲渡を制限。 | デジタルチケット、限定グッズ |
ソリューションの種類ごとに詳しく解説します。
購入行動・異常検知型AI
購入行動・異常検知型AIの仕組みは、購入者の動向をAIが分析することで、転売を防止する方法です。
まずアカウントに紐づいた購入履歴や行動パターンをAIが分析します。分析の結果によって転売の兆候を検出した場合は、該当アカウントでの商品購入はできません。
また、通常とは異なる大量購入や短期間での複数注文などについてもAIによって検出が可能です。異常行動を発見次第、商品購入ができなくなります。
主な用途としては、ECサイトや家電、限定商品の販売管理などです。代表例としては、AIを活用した以下のような不正検知ツールが挙げられます。
- BUY-X
- O-PLUX
- 売れるD2C AI不正チェッカーなど
購入行動・異常検知型AIのチェックツールには、それぞれ一長一短があるため、自社に最適なツールを選択しなければなりません。
顔認証・生体認証型AI
顔認証・生体認証型AIは、近年コンサート会場やスポーツイベントなどでのなりすましや不正転売を防ぐ目的で活用されています。
基本的な仕組みは、チケット購入時や入場時に顔認証を行います。事前に登録した顔情報とチケットを紐づけることにより、なりすましや不正転売の物理的な排除が可能です。
ただし、基本的にチケットの譲渡は禁止されており、転売目的でなくチケットを譲渡した場合にもチケットが無効となります。
以下のようなものが代表例です。
- SECURE AC
- デジタル認証アプリ連携
近年は多くのコンサートなどで活用されるようになり、転売目的での購入ができなくなってきました。ただし、認証時のトラブルもあるため、トラブル対応も必要です。
画像認識型AI
サイン入りグッズなどの転売防止には、画像認識型AIが有効です。
画像認識型AIは商品画像をAIが解析し、出品画像と事前登録画像を照合します。とくにサイン入りグッズや限定品の営利目的での購入は、多くの場合原則禁止です。
したがって、転売サイトやフリマサイトにサイン入りグッズや限定品が出品されることが問題なため、サイト側で自動検出できる仕組みになっています。
画像認識型AIを活用した代表例は、川崎フロンターレのサイン入りグッズAI判定システムです。現在は画像認識だけでなく、NFT技術の活用も検討されています。
ボット検知・アクセス監視型AI
ボット検知・アクセス監視型AIは、人気商品の販売時やオンラインチケット販売などに活用されている転売防止ソリューションです。
購入時のアクセスログや行動データを解析することで、転売を防止します。アクセスログや公道データを解析すれば、ボットによる自動購入や大量アクセスをAIがリアルタイムで検知できるため、転売の遮断が可能です。
代表例としては、下記のようなものが挙げられます。
- SpiderAF
- 海外EC向けBot対策製品など
SpiderAFは不正転売だけでなく、AI時代のあらゆる脅威からマーケティングを守るプラットフォームです。
ブロックチェーン・NFT連携型
ブロックチェーン・NFT連携型は、デジタルチケットの転売防止や限定グッズの所有権管理に活用されています。
商品やチケットにNFT(非代替性トークン)を付与し、所有者情報をブロックチェーンで管理する仕組みです。正規流通以外の商品の譲渡や転売を技術的に制限できます。
代表例は、NFTチケットシステムです。NFTチケットシステムを活用することで、チケットの固有性と取引の透明性を確保できます。また、アーティストとファンとの絆を深める手段としても注目されているシステムです。
ただし、ブロックチェーン・NFT連携型の転売防止ソリューションは、技術が難しいことや手数料がかかることなどの課題があります。
転売対策の導入時に注意すべき5つのポイント
AIによる転売対策の導入時には、いくつかの注意しなければならないことがあります。なかでも重要なものは、以下の5つです。
- 誤検知・過剰検知:正規ユーザーの排除リスク
- 法的・倫理的配慮:権利侵害や差別の排除、個人情報の適切な管理
- UI・UX設計:正規ユーザーの負担軽減設計
- AI過信防止:人による監視やレビュー体制
- 継続的な精度向上:モデルのアップデートと学習
注意点を意識せずに転売対策を導入すると、思った以上にコストがかかったり、ユーザーが不便を感じたりするかもしれません。ただ転売を防止するだけでなく、注意点を考慮してよりよい状態で転売対策を行ってください。
上記の5点について、詳しく解説します。
誤検知・過剰検知のリスク
AIを活用した転売対策には、誤検知や過剰検知のリスクを伴います。誤検知や過剰検知のリスクを排除するには、AIの検知精度や運用ルールの調整が重要です。
AIを活用した転売対策は、大量のデータによって異常な購買行動やボットによる購入を検知できる仕組みです。一方で、大量のデータのなかには不確かな情報もあり、誤検知や過剰検知によって正規のユーザーを誤って排除するリスクがあります。
誤検知や過剰検知が発生した場合、正規顧客の満足度低下やクレームとなるでしょう。リスク排除のため、定期的なチューニングを実施するようにしてください。
法的・倫理的配慮
転売対策にAIを活用する際には法的・倫理的配慮を怠ってはなりません。
転売対策を強化しようと考えると、利用者の権利や業界のルールにまで踏み込む必要があります。
たとえば購入履歴や行動パターン、本人確認情報などの個人データを扱う際には、個人情報の適切な管理と法令順守が必須です。また、不当な差別や排除が起きないように注意しましょう。
法的・倫理的配慮には、AIの判定基準の透明化が重要な鍵を握ります。利用者のプライバシーを十分に配慮し、情報の取得や保存方法、利用範囲を明確にしましょう。
UI設計とユーザー体験(UX)への影響
AIを活用した転売対策では、UI設計とユーザー体験(UX)への影響も考慮しなければなりません。
たとえばAIで人間とボットを自動判別するには、CAPTCHAや本人確認などの追加認証が必要です。一方で、CAPTCHAや本人確認などの追加認証を多用すると、ユーザーの負担になるため、正規ユーザーの離脱や不満につながる可能性があります。
あなたも判別の難しい文字の入力や難易度の高いCAPTCHAを経験したことがあるのではないでしょうか。
AIを活用した転売対策では、できる限り正規ユーザーには負担をかけない設計を心がけなければなりません。CAPTCHA強化や購入制限は、顧客視点とバランスをとったUI設計が必要です。
AIの過信と人による監視の併用
転売対策においてAIを活用する際、AIが万能ではないことを意識しておかなければなりません。転売の技術は常に進歩しているため、AIの過信は禁物です。
従来の転売手法とは異なる方法が考え出される可能性もあるため、AIでは対応できない可能性もあります。したがって、AIだけに頼らず、定期的な人の監視も必要です。
また、AIの学習データについても、判定結果のレビュー体制を整えなければなりません。
継続的な精度向上とアップデート
AIを活用した転売対策は、継続的な精度向上とアップデートを実施しなければなりません。なぜなら、転売手法は日々進化し、巧妙化しているからです。
最新の転売手法に対応するには、AIモデル学習データの更新が必要です。定期的に学習データを更新し、精度を向上しなければなりません。
学習データは膨大な量が必要となり、導入後のPDCAも非常に重要です。
転売防止事例5選
AIを活用した転売防止の成功事例を紹介します。転売による問題が増えているため、昨今では多くの事例が報告されていますが、そのなかから以下5つの事例を厳選しました。
- メルカリの政府備蓄米転売禁止AIシステム
- カメラのキタムラのAI転売対策
- チケット転売対策にAIを活用
- サイン入りグッズの画像判定で転売対策
- 健康食品ECサイトの転売対策
それぞれもう少し詳しく解説します。
メルカリの政府備蓄米転売禁止AIシステム
メルカリは2025年5月に、政府備蓄米の転売対策としてAI監視システムを導入。コメの転売が問題視されるなか政府備蓄米の販売が開始され、備蓄米の転売対策が必要となりました。
AI監視システムを導入したことにより、政府備蓄米の転売については完全禁止となっています。
また、メルカリだけでなくLINEヤフーも同様に転売対策を導入し、備蓄米に対する転売対策を実施しました。LINEヤフーが転売対策を実施した対象サイトは『Yahoo!オークション』と『Yahoo!フリマ』です。
違反出品を検知した際には、自動で出品を停止し、違反者にはアカウント制限を実施しています。
転売対策のシステムは、画像認識と自然言語処理(NLP)を組み合わせたものです。出品画像や説明文から「政府備蓄米」などのキーワードやパッケージデザインを高精度で検出できます。検出精度は約95%であるため、大きな抑止力となっているでしょう。
カメラのキタムラのAI転売対策
カメラのキタムラでは、2023年3月にAI不正検知ツール『O-PLUX』を導入し、転売対策を行っています。
以前よりカメラやカメラ用のレンズなどは換金性が高く、転売の温床となっていました。また、近年はカメラ自体の価格も上昇傾向であり、不正被害の標的になりやすい状況です。
AI不正検知ツール『O-PLUX』では、注文を以下の3種類に振り分けて判別しています。
- NG(キャンセル)
- OK(出荷)
- Review(有人確認)
カメラのキタムラでは、転売対策によって転売目的の大量買い占めや大量キャンセルをほぼ自動で検知できるようになりました。従来はすべて有人での確認を実施していたため、ツール導入後はチェック時間が大幅に減少しています。
参考:カメラのキタムラが不正注文検知サービス「O-PLUX」を導入
関連記事 3Dセキュア2.0とは?義務化に向けて知っておきたいこと
チケット転売対策にAIを活用
近年、コンサートチケットやスポーツイベントのチケット転売が社会問題となっています。アイドルグループのコンサートチケットが転売サイトで10万円や20万円で転売されているケースも少なくありません。
- チケットの転売対策には、主に2種類の方法が導入されています。
顔認証技術の導入による対策
事前登録やリアルタイム顔認証を活用した転売対策方法です。事前に登録した写真と当日照合し、異なる場合にはチケットが無効になります。 - デジタルチケットとブロックチェーン技術の組み合わせで対策
ブロックチェーンは、チケットがどのように取引されてきたかをすべて記録するものです。チケットの譲渡履歴を記録するため、不正な転売の検知が可能になります。
チケットの転売対策については、下記の記事も参考にしてください。
関連記事 チケット不正転売の防止施策まとめ
サイン入りグッズの画像判定で転売対策
多くのスポーツ業界では、サイン入りグッズの営利目的での入手を禁止していますが、不正転売が後を絶ちませんでした。
川崎フロンターレでは、サイン入りグッズの転売を重要課題と考え、エフィシエントが開発した転売抑止AIエンジンを導入しています。転売抑止AIエンジンは、取り込んだ画像からサイン部分を識別し、配布前の画像と照らし合わせて検出するシステムです。
実験では97%以上の精度を達成したため、2022年5月23日より導入・運用を開始しました。導入後は高額転売だけでなく、転売サイトに出回る偽物の検出も可能となっています。
今後はNFT技術を導入し、さらに転売対策を強化する予定です。
参考:川崎フロンターレがユニフォーム転売抑止AIシステムを導入
健康食品ECサイトの転売対策
さくらフォレストが運営する健康食品ECサイト『さくらの森』では、主に「初回限定価格品」を狙った不正注文による転売対策を行っています。
さくらフォレストが活用しているのは、カメラのキタムラと同じ不正検知サービス『O-PLUX』です。『O-PLUX』は機械学習とルールベースAIを組み合わせた独自ロジックとなっています。
AIによる転売対策の導入により、クレジットカード不正利用や悪質転売、後払い未払いなどの不正注文をリアルタイムに検知できるようになりました。また、精度の高い転売対策を実現するとともに広告費のコストダウンにもつながっています。
参考:健康食品ECサイト「さくらの森」が「O-PLUX」の導入で転売対策を強化
まとめ〜転売対策は「守り」から「攻め」の施策へ〜
転売対策は、かつては受動的なセキュリティ対応と捉えられがちでしたが、近年は“攻め”の戦略にも活用できるフェーズに移行しつつあります。
転売対策の導入により、商品が本当に必要な顧客の手に届くようになることで、ブランド価値の毀損防止だけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化にもつながります。
EC業界をはじめとする各企業にとって、AIによる転売対策は今後ますます不可欠な取り組みとなっていくでしょう。
本記事で紹介した転売対策事例や最新の技術トレンドを参考に、自社に最適な施策を検討する第一歩としていただければ幸いです。