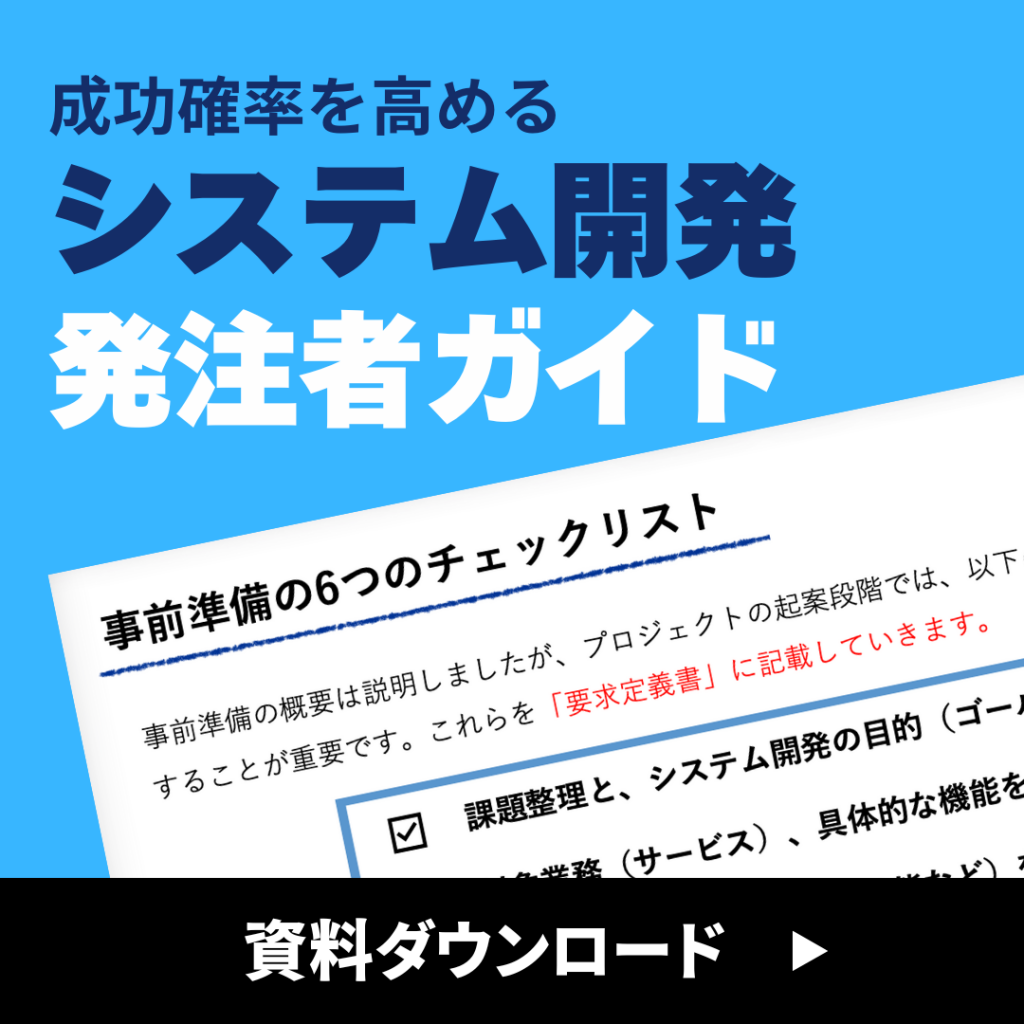2016年、「VR元年」と呼ばれた年を覚えていますでしょうか。あれからもう9年。VRが目に留まることは多くなり、特に「マルチユーザーVR」―つまり複数人が同じ空間でVRを体験する仕組みは、大きな注目を集めてきました。
産業界の研修や教育、エンタメ施設などで「みんなでVRを体験する」事例は次々と登場しましたが、現在を振り返るとちょっと意外な光景が見えてきます。
産業界では自動車メーカーやWalmartのような“大手中心”で活用が進み、一方、エンタメ分野では、かつて話題になった都内のVRをテーマとした屋内テーマパークが閉鎖されるなど、縮小傾向も目立っています。
今回は「マルチユーザーVRのいま」を整理しながら、次にどう進めばいいのか?をテックファームの考察とともに解説していきます。
マルチユーザーVR事例
まずは近年の、国内外の代表的な事例から挙げていきます。
国内産業界の事例
国内からは、大手自動車メーカーの事例をピックアップ
複数の工場/部署でのVR/MRによる研修・設計検討【トヨタ自動車】
生産現場の安全教育や設計レビュー・MRを使った作業支援などで大規模な導入・試行を実施。
HoloLens等のMRやVRを組み合わせた事例が公開されています。複数人での利用を想定した業務フローに組み込まれているようです。
参考:https://arinsider.co/2020/09/23/case-study-toyota-makes-mixed-realty-magic/
工場のMR活用、VRショールーム/体験での同時アクセス【日産自動車】
生産トレーニングでMRを使い指導時間短縮などの効果を出しているほか、VRChat等を使ったバーチャル体験を多数のユーザーが訪れる形で公開。研修用途は現場複数名での利用事例があるとのことです。
参考:https://www.nissan-global.com/EN/STORIES/RELEASES/nissan-is-evolving-with-mr-technology/
海外の事例
続いて、スケールの大きさが目立つ海外の事例を紹介していきます。
数万単位の従業員を対象にVR研修を導入。全社展開を見据えた「大規模配備」【Walmart】
Walmartは2017〜以降、従業員トレーニングにVRを積極導入。パイロットから全社展開へ移行し、複数の従業員を同時に訓練する仕組みや大規模配備(数千〜数万台規模)の設計に至っています。
大規模で“拡張可能な”エコシステム設計に舵を切った点が特徴です。
参考:https://corporate.walmart.com/news/2018/09/20/how-vr-is-transforming-the-way-we-train-associates
共同作業・操縦室トレーニング/複数人でのリモート共同訓練【Boeing】
航空宇宙分野で高精度VR/シミュレータを複数人で使う事例。遠隔地の複数受講者が同じ仮想空間で訓練・検証する取り組みが進んでいます。
エンタメ分野の事例
このセクションではエンタメ分野の事例を紹介していきます。
Bandai Namco『VR ZONE』シリーズ
国内で有名だったのはBandai Namcoの「VR ZONE」。2017年に新宿で開業し大きな話題になりましたが、その後は閉鎖や再編が続きました。
2017年に話題になった大型VR施設は来館型のグループ体験を前提にしていました。(※VR ZONE Shinjukuは現在は閉鎖されております。)
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000033062.html
関連記事 VR研修が進まない“現場の本音”とは?
Sandbox VR(グループ向けマルチプレイヤーLBE)
海外ではSandbox VRなどの施設がまだ頑張っています。6人前後で協力・対戦できる仕組みで、グループ体験に特化して存続・拡大するチェーンもあります。
6人程度のグループで協力・対戦する商用施設。採算や運営モデルを再設計して存続・拡張するチェーンもあり、成長と縮小が混在しています。
産業界のマルチユーザーVRの導入は、なぜ“大手に留まり続ける”のか?
考察し始めると、以下のような背景が見えてきます。
- コストが高い
- 業務に組み込む体制が必要
- 専門ベンダー不足
それぞれ、解説していきます。
コストが高い
VRゴーグルを何十台も揃えるのはもちろん、ソフトやコンテンツ開発費もかかります。これを回収できるのは規模の大きい企業(大量の受講者)に限られてきたかもしれません。
WalmartやBoeingの事例は“スケールして初めて投資対効果が出る”モデルです。
業務に組み込む体制が必要
“VRの単なる大人数の利用”ではなく、例えば研修用VRであれば、教育カリキュラムや評価とリンクさせたいとするところ、ITや人材体制が必須。これも大企業ならではなのかもしれません。
専門ベンダー不足
業務ごとに最適化されたVRコンテンツが必要ですが、業界知識、研修メソッドへの知見、に長けたVR開発ベンダーは限られています。大企業ならVRの導入にあたって、社内の人材・チームを割り当てられることがあるかもしれません。
なぜエンタメ施設は閉鎖が相次ぐのか?
エンタメでの定着が伸び悩む主な要因は以下の5つです。
- COVID-19の直撃
- 高い固定費と相対的に低い回転率
- リピート性の確保が難しい
- 消費者側のハード普及と在宅体験の向上
- 運営リスク
それぞれ、解説していきます。
COVID-19の直撃
密集・接触が懸念され、2020年前後に多くのLBE(ロケーションベース エンターテインメント)施設が一時閉鎖、あるいは恒久閉鎖に至った経緯があります。
高い固定費と相対的に低い回転率
LBEは面積あたりの売上を高める必要があるが、ヘッドセットの消耗・交換、清掃、コンテンツ更新料など固定費が高く採算が厳しいため、業界分析でも「ロケーション型は運営ノウハウと高い稼働率が必須」と指摘されています。
リピート性の確保が難しい
エンタメ的VRは「初回は驚くが、次に来る動機付け」をどう作るかが課題です。新コンテンツ投入が必要で、これもコスト増。業界論でも“ヒットコンテンツと継続的なコンテンツ投資が鍵”とされています。
消費者側のハード普及と在宅体験の向上
家庭用VR(Quest系など)が進化し、個人での体験格差が縮まると「わざわざ外で試す動機」が薄れるケースもあります。LBEは“家庭で得られない付加価値”を提供し続ける必要があります。
運営リスク
ヘッドセット共有による衛生感情、酔い・安全管理、クレーム対応のコストが運営負担になることが挙げられます。コロナ以降は衛生対策コストも増加しています。
マルチユーザーVR普及のポイント
ここまで読むと、産業界もエンタメ分野も「マルチユーザーVRは普及しないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、以下にまとめたヒントで、みなさまとVRの拡がりを一緒に考えてみる余地もありそうです。
産業界のヒント
- パッケージ化・標準化されたVR研修ツールを使えば、大企業でなくとも導入しやすくなるはず!
- 工場や設備の3Dデータ化を進めて、デジタルツインまで応用すれば投資効果が見えやすい1?
- KPI(研修時間短縮・事故減少)を数値で示してみることもポイント。
エンタメのヒント
- Sandbox VRのように「グループで来る、使う意味」を最大限考える。
- VRの運用管理者が一人でも運用できるまで効率化! コストを抑えてみる。
- レジャーだけでなく「法人研修=チームビルディング、ゲーミフィケーション」までの多用途化を考えてみる?
まとめ
産業界では大企業が中心となって導入していますが、今後は「標準化」「効率化」「定量化」がキーワードになりそうです。エンタメでは淘汰が進む一方で、「グループ体験」はもちろん、「多用途化」まで活路を見出したいところです。
共通して言えるのは、効率的な3Dデータ化、運営効率化、効果の定量化。
これらをデジタル施策で解決できれば、「大手しかできない」「一度きりの体験で終わる」等から脱却できるはずです。
マルチユーザーVRはまだまだ進化途中。次のステージは「誰もが気軽に使える仕組み」をどう作るかにかかっているのかもしれません。
当社テックファームでは、マルチユーザーVRの利用をご検討されているお客様向けに“運営効率化の一助”となる
XR統合管理ツール『OneXR』をリリース、ご紹介しております。
ご興味ありましたら是非ぜひ、お気軽にお問い合わせください。