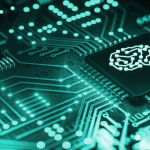マーケティング戦略において、非常に効果的な「STP(エスティ―ピー)分析」。
「聞いたことはあるけど、どうやって活用すればいいのか良くわからない」という方もいるでしょう。
STP分析は、正しく活用することで自社が狙うべき市場や競合他社との比較分析ができ、効率的に利益をあげる解決策の糸口となります。
そこで本記事では、STP分析の概要や使い方について、成功事例とともに解説します。マーケティングに関して悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
STP分析とは?
STP分析とは、アメリカの経営学者でマーケティングの先駆者であるフィリップ・コトラー氏が編み出した分析手法のことです。
STPのそれぞれの意味は、以下の通りです。
- S:Segmentation(市場の細分化)
- T:Targeting(狙うべき市場を決める)
- P:Positioning(自社の現在の立ち位置を確認)
商品やサービスの提供を開始する前や、市場に変化が起こったときに上記3点を分析することで、自社を優位的な位置に導く戦略を見つけることができます。
STP分析はマーケティングにどう活かす?
STP分析は、マーケティング戦略を立案する基盤となるフレームワークです。具体的にどのような点がマーケティングに効果的なのか解説します。
顧客ニーズの理解を深める
STP分析では、分析を通して市場をいろいろな角度から細分化するので、顧客が何を求めているかの理解を深めることができます。
これまでなんとなく「この商品がよく売れるな」と思っていたものも、「どんな顧客がどの時期にどれくらい購入してくれる」といったように、顧客のニーズ傾向を可視化することが可能です。
現代はインターネットなどを駆使し、個人が簡単に情報を収集できる時代です。そのため、顧客ごとにパーソナライズされたアプローチが重要といえます。的確に顧客ニーズに応えることができなければ、競争の中で注目を集めることはできません。
その点、STP分析では市場を細かく分析することで顧客のニーズを把握できるため、正しいマーケティング施策の立案・実施にも役立つでしょう。
自社の強みを改めて明確化する
STP分析で具体的な市場や顧客のニーズを知ることで、自社製品の強みや魅力を整理することができます。
自社のアピールポイントがしっかり把握できていないと、上手く販促することができません。また、社内で認識がバラついていると、間違った戦略で売り込んでしまう恐れもあるでしょう。
自社の強みが明確になれば、戦うべき市場やアプローチする対象も明確になり、効率的なマーケティング戦略を立てることにもつながります。
他社製品について知り差別化を考える
STP分析をすると、他社製品の強みやアピールの方法を知ることができます。
すでに知名度の高い他社と似たような商材を打ち出しても、競争で優位に立つことはできません。自社製品は、競合他社の中でどのような立ち位置かを把握し、作戦を立てることが重要です。
製品の特性や価格などを比較して、何を軸に差別化すれば利益を上げられるかを考えましょう。
STP分析のやり方3STEP
ここでは、実際にSTP分析をする際のやり方をステップ別に解説します。
STEP1:セグメンテーション
まずは、市場を顧客のニーズや特性ごとで細分化し、グループ分けする「セグメンテーション」を行いましょう。
たとえば、BtoC企業の場合は、一般的に以下4つの方法で分類します。
- 人口統計的変数(デモグラフィック変数)
性別・年齢・職業・家族構成・収入など基本的な人の情報を基に分類する方法。自社の商材と相性の良いターゲットに絞ります。 - 地理的変数(ジオグラフィック変数)
国・地域・都市・気候・文化など地理的な情報を基に分類する方法。例えば国内でも東北と近畿地方で気候が大きく違うなどのようにグループ分けをします。 - 行動的変数(ビヘイビアル変数)
個人の買い物頻度・動機・購入金額など行動パターンを基に分類する方法。新規かリピーターか、どういう経緯でどのくらい買うかなどが分かれば、アプローチ方法のヒントになります。 - 心理的変数(サイコグラフィック変数)
価値観・性格・趣味・習慣など個人の心理的な要素を基に分類する方法。例として、趣味はインドアかアウトドアか。飲酒の有無、飲むとして家なのか外なのかなどです。
BtoB形態の場合は、上記の消費財市場の分類方法に加えて、以下4つの生産財市場の指標を使うことがあります。
- 人口動態変数(企業の規模や業種に分ける)
- オペレーティング変数(顧客のスキルや使用頻度で分ける)
- 購買アプローチ変数(顧客が購買する基準や意欲で分ける)
- 状況要因変数(緊急性や受注量で分ける)
4Rの原則でグループ分けの有効性を確認
セグメンテーションができたら、分けたグループが4Rの原則を満たしているか確認しましょう。
4Rとは、以下4つのポイントのことを指します。それぞれのポイントに沿って、セグメントが正しく行えているかチェックしてください。
- Rank(優先順位)
優先度の付け方は自社のマーケティング戦略に沿っているか。 - Realistic(有効性)
十分な売上や利益が見込める市場規模かどうか。 - Reach(到達の可能性)
自社製品の魅力や宣伝が的確にターゲットに伝わるか。 - Responce(測定の可能性)
対象の市場規模や特性の測定、マーケティング戦略を実施した後の反応を測定できるのか。
STEP2:ターゲティング
次に、セグメンテーションで分類した市場の中から、自社が狙いを定めるべき顧客層を絞る「ターゲティング」を行います。
ターゲティングにおいては、自社のコンセプトや強みがマッチしていて、成功すると予想できる市場を選定することが重要です。なお、ターゲティングの段階では主に以下3つのマーケティング方法が使われます。
- 無差別型マーケティング
セグメンテーションでグループ分けした市場は無視して、あらゆるターゲットに同じ商材を提供し、動向を見る方法。認知度が一気に広がる一方、宣伝・広告費が膨大にかかるため、大手企業や消費者が多い食料品などに適した方法です。 - 差別型マーケティング
セグメンテーションで分けた市場のニーズごとに商材を用意し、提供する方法。細かな対応により、固定顧客の獲得率が上がり、安定的な売上につながります。しかし、それぞれのニーズに合った価格や機能などを変えなければならず、手間とコストがかかるため、規模の大きい企業向けの方法といえます。 - 集中型マーケティング
1つ、もしくは少数の市場に絞ってマーケティングを行う方法。特定の顧客ニーズを深掘りして質の高い商材を提供することで、ターゲットの満足度が上がります。高級路線やニッチな製品など市場が小さい場合や、熱狂的なファンがついている場合に有効的です。
セグメンテーションで分類した市場に対して、どのようにアプローチするかは企業によって異なります。ターゲティングに正解はないので、自社製品の強みやマーケティング方針に合った方法を選ぶとよいでしょう。
STEP3:ポジショニング
最後のステップは、ターゲットに決めた市場内において他社との比較をし、自社の立ち位置を明確にする「ポジショニング」です。この段階では、競合他社製品の価格や機能を調査し、自社の優位点を探ります。
ポジショニングの分析には、ポジションマップを作成するのが一般的です。縦軸・横軸のマトリクス図に価格・品質・機能などの比較項目を設定し、自社と競合他社間の位置を確認します。
なお、ポジショニングにおいては、自社製品の魅力が発揮されるポジションを見つけることが重要です。知名度がある会社がすでに存在する場合や圧倒的シェアを誇る商品がある場合は、高利益を産むのは簡単ではありません。感覚ではなくデータに基づいて分析し、差別化を図りましょう。
また、軸となる比較要素を増やしすぎると、本当に必要なものがわからなくなってしまうため、なるべくシンプルに分析することをおすすめします。
STP分析の結果を4P分析に反映
STP分析が終わったら、マーケティングミックス(4P)というフレームワークに結果を反映しましょう。
「4P」のそれぞれの意味は、以下の通りです。
- Product(製品・サービス)
- Price(価格)
- Place(販売の場所・方法)
- Promotion(販促)
4P分析は、マーケティング施策の立案に役立ちます。活用する際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 旧製品よりも改善されているか
- 顧客が満足できる価値提供ができているか
- 競合他社と比較して価格は適切か
- 広告・宣伝方法は効果的にできているか
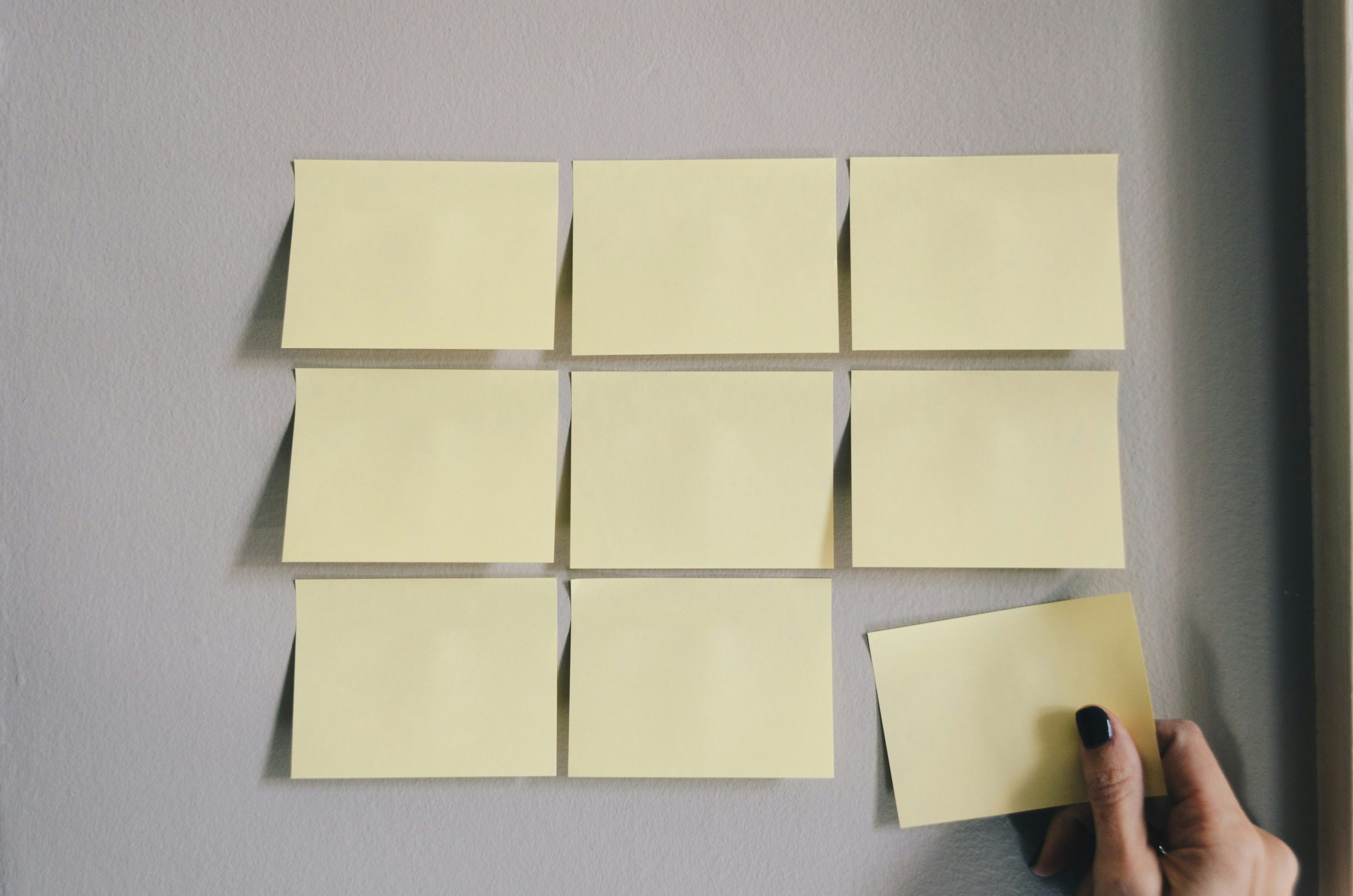
STP分析のポイント・注意点
ここからは、STP分析を正しく活用するためのポイントや注意点をステップごとに解説します。
なお、STP分析を行う際は必ず「S(セグメンテーション)→T(ターゲティング)→P(ポジショニング)」の順番でなければならないわけではありません。自社のやりやすいように順番を変えて行いましょう。
ただし、各項目の連動性は意識してください。単体で分けてしまうと矛盾が生まれる可能性があります。全ての分析内容が嚙み合っているかの確認をしながら進めましょう。
セグメンテーションのポイント・注意点
セグメンテーションにおけるポイント・注意点は、以下の通りです。
過剰な細分化を避ける
顧客ニーズに合わせて市場のグループ分けをする際、細かく分けすぎると時間がかかるうえ、注目すべき市場を見失ってしまいます。自社の強みにマッチしているかどうかを判断しながら、細分化の範囲を考えましょう。
適切な変数を選択する
効果的な分析結果を得るには、自社の商材や実施目的に適した変数のみを選び組み合わせましょう。
データに基づいた分析をする
売り手側の想像と実際に顧客が求めているものには、ギャップがあることもあります。したがって先入観や主観的な考えを除いて分析することが重要です。推測ではなく、調査や統計などのデータに基づいて分析をし、客観的な判断をしましょう。
ターゲティングのポイント・注意点
ターゲティングにおけるポイント・注意点は、以下の通りです。
競合の状況や参入障壁なども考慮
自社がターゲットを絞った市場の規模や成長性が大きいとしても、大手のシェア率が圧倒的な場合や、競合他社が多い場合は難易度が高くなります。また、トップの会社の特性が、他の会社に真似できないようなものである場合、将来的にも優位に立つことは難しいでしょう。
競争優位性を築ける市場をターゲットに
競合他社と自社の商材を比較し、優位に立てそうな市場を選びましょう。また、市場は1つに絞らず複数候補を上げておき、自社の成長や競合他社の増加など変化に合わせてターゲットを変えるのもおすすめです。
ターゲット市場における収益性も考慮
自社が狙う顧客層は収益の見込みがあるのか、しっかりと予測することも重要です。ニッチな商材すぎて求める顧客数が少ない場合や、すでに参入企業が多すぎる場合、十分な収益は見込めません。また、現時点で良好な市場な場合でも他社の将来動向を予想して、先に対抗的な差別化をしておくと効果的です。
ポジショニングのポイント・注意点
ポジショニングにおけるポイント・注意点は、以下の通りです。
顧客視点を忘れない
自社のポジションを分析するうえでは、顧客視点を忘れないようにしてください。自社がどう思うのかではなく、顧客が自社の商材に対してどのような位置づけにするのかを分析することが大切です。売り手側の感覚だけで考えると、的外れな戦略立案につながりかねません。
差別化ポイントを明確に
顧客目線で自社の位置がわかったうえで、どのような強みが他社と差別化できるのかを考えましょう。顧客に選ばれるためには、他社にはない魅力があるということを明確に伝えることが重要です。
ブランドイメージやメッセージに一貫性を持たせる
市場トップに立ちたいからといって、自社が目指す方向性は見失わないようにしましょう。多くの戦略を加えすぎて、ブランドイメージがぶれては顧客も困惑してしまいます。自社の独自性を効果的に伝える方法を考えることも必要です。
STP分析を活用したマーケティング施策の成功事例
ここでは、STP分析を活用したことでマーケティングに成功した企業の事例をいくつか紹介します。実例をSTP分析の使い方の参考にしてみてはいかがでしょうか。
スターバックスコーヒー
スターバックスコーヒーは、フリーWi-Fi完備で学校や職場、家以外の居場所である「サードプレイス(第3の居場所)」としてマーケティングに成功している例の一つです。
スターバックスで、STPをそれぞれどのように分析しているのか見ていきましょう。
セグメンテーション
10代〜70代と幅広い年齢層、男女が対象。そこから学生・主婦・会社員・フリーランス・ノマドワーカー・高齢者に細分化しています。
ターゲティング
主なターゲットは主要都市などの大きい街で、平均もしくはそれ以上の収入があるオフィスワーカー。以下、時間帯別のターゲットです。
| 朝 | 出勤前にデスク仕事が必要な人や高齢者 |
| 昼 | ノマドワーカーや主婦 |
| 夕方~夜 | 帰宅前のオフィスワーカーや学生 |
| 休日 | 買い物途中の休憩やカップルなど |
ポジショニング
一般的なカフェと比較して快適に長居ができるという差別化をし、位置を確立しています。その他、徹底的な質の高い接客・オリジナルグッズ販売なども優位性を保っているポイントです。
ユニクロ
ユニクロも、STP分析によってマーケティングに成功している事例の一つです。ユニクロのSTP分析は特徴的で、一般的な方法と少し違います。年齢や性別などで市場の細分化をせず、具体的な顧客のニーズでグループ分けをしているのです。
「日常的でシンプル。リーズナブルだけど質が良くて長持ちする」など、一般的な要望に合わせた商品開発に集中したことによって、事業拡大に成功しています。
ユニクロのSTP分析詳細を見ていきましょう。
セグメンテーション
市場は次のように細分化しています。
- 高品質で長持ちするけど高くない服が欲しい人
- 機能性とコストパフォーマンスが良い服が欲しい人
- 日常的なシンプルな服が欲しい人
ターゲティング
- シンプルでカジュアルなデザインを好む顧客層
- ベーシックだけど高品質を好む顧客層
ポジショニング
流行ファッションは追わず、廃れないシンプルなデザインに注力することで年齢・性別関係なく購入できることに特化。これにより、競合他社になり得た大手ブランド「ZARA」や「H&M」と絶対的な違いを確立し、現在の成功を持続しています。
コカ・コーラ
コカ・コーラ株式会社は、コーラだけではなく幅広い飲料品の開発・販売を行っています。コーヒーの「ジョージア」やミネラルウォーターの「いろはす」もコカ・コーラ社発です。
時代の変化にも合わせてヒット商品を生み出し続けるSTP分析方法を見てみましょう。
セグメンテーション
単に飲料水で分類するのではなく「食事に合わせた飲料」でグループ分けしています。和食に合う飲料や、ダイエット・健康に適した飲料などでセグメントを細分化。「綾鷹」や「トクホ」が代表的です。
ターゲティング
市場のニーズごとに違う商品を用意して販売する「差別型マーケティング」。同じ商品を市場の分類に関係なく販売する「無差別型マーケティング」の2つを実施しています。
ポジショニング
コカ・コーラという歴史あるブランドイメージを保ちつつ、新しい商品にも挑戦することで、リピーターと新規顧客を同時に獲得しています。また、ただの飲料水ではなく「食事に合う飲料水」を提供する会社という差別化で、確固たる位置づけをキープしています。
マーケティングフレームワークにおけるSTP分析の位置づけ
マーケティングフレームワークには、環境分析・基本戦略・具体的施策の3段階があります。STP分析は、第2段階の基本戦略で使うフレームワークです。
また、よく使われる「マーケティングミックス(4P)」は、最終段階の具体的施策で使用するフレームワークとされています。しかし、実際にはSTP分析と4Pは同時に実施する方が効率的です。
STP分析と他フレームワークの併用
マーケティングにおいて、STP分析だけでは市場への参入や事業の拡大が難しいと感じる結果になることもあります。そこで他のフレームワークも併用すれば、多角的な面から分析ができ、新たな発見や気づきが得られるかもしれません。
ここでは、STP分析との併用におすすめのマーケティングフレームワークを紹介します。
SWOT分析(戦略目標)
SWOT分析とは、内部環境(自社)と外部環境(市場)を以下の「SWOT」の4要素に当てはめて分析する手法です。
- Strength(強み)
- Weekness(弱み)
- Oppotunity(機会)
- Threat(脅威)
状況が変化しても臨機応変に使える手法のため、外部環境の機会と脅威に対して自社の強みをどのように活かし、弱みをカバーできるかを分析するのに役立ちます。
PEST分析(マクロ環境分析)
PEST分析は、外部環境を以下4つの要素に当てはめて分析するフレームワークです。
- Politics(政治:法律や政策など)
- Economy(経済:景気・物価・家計消費の動向など)
- Society(社会:世論・流行・人口動態など)
- Technology(技術:技術革新など)
自社の課題発見、市場状況の把握、未来予測などに役立ちます。
3C分析(業界環境分析)
3C分析とは、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3Cの要素で分析するフレームワークです。
市場における自社の位置づけを把握すると同時に、事業を成功につなげるヒントを見つけるのに役立ちます。
5フォース分析
5フォース分析とは、新規参入事業者・売り手・競合他社・買い手・代替品の5分野を整理し、分析する手法です。
分析した結果を通して自社への脅威となる要素がわかるので、対策を講じるのに役立ちます。
まとめ| STP分析を正しく活用して効果的なマーケティングを
本記事では、STP分析について詳しく解説しました。STP分析を使えば、自社を優位に導くマーケティング戦略が見えてくるはずです。
ただし、感覚で判断せずデータに基づいて分析しなければ、正確な結果は得られません。加えて、正しい活用方法や注意点を確認することも大切です。
またSTP分析だけではなく、他のフレームワークも併用して多角的に分析をすることでさらに事業成功の可能性を広げられるでしょう。