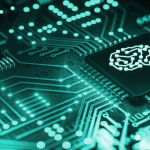近年、XR技術は国内の製造業や建築業、教育、エンタメ業界、福祉、医療などのあらゆる産業分野で利用されるようになってきました。一方で、まだ身近に感じられない人も多いかもしれません。
加えて、国内のXR技術が進歩してきたことで、今後は我々の生活に影響を与えることは確実です。日常生活でXRデバイスを使用する日も近いでしょう。
本記事ではXRを利用する際に必要となる国内のXRデバイスについて詳しく解説しています。XRデバイスの種類や特徴を紹介するとともに、実際にビジネスに活用している事例も紹介していきます。
XRの活用により、人手不足やコスト削減などのメリットが得られます。ぜひ事例を参考にして、XRを活用してみてください。
<目次>
XRデバイスとは?種類や特徴、選定ポイントを解説
・XRデバイスとは?
・XRデバイスの種類
・国内XRデバイスの特徴
・国内XRデバイスの選定ポイント
国内XRデバイスの最新5選!人気モデルの特徴と性能を詳しく解説
・AIによる翻訳が可能『dynaEdge XR1』(Dynabook)
・約125gのXRデバイス『MiRZA』(NTTコノキューデバイス)
・高解像度で没入感のある体験を実現『PlayStation VR2』(Sony)
・超軽量VRヘッドセット『MeganeX superlight 8K』(Shiftall)
・LTE搭載の国産スマートグラス『InfoLinker3』(桜井株式会社)
XRデバイスの活用業界
・ANAがVR訓練シミュレーターを導入
・VRを活用したリハビリのサポート
・InfoLinker3を警備業務に活用
XRデバイスとは?種類や特徴、選定ポイントを解説
XRとは、VR(virtual reality)・AR(Augmented Reality)・MR(Mixed Reality)・SR(Substitutional Reality)技術の総称です。
VR:仮想現実
AR:拡張現実
MR:複合現実
SR:代替現実
それぞれの詳細については、下記の記事を参考にしてください。
参考:【XR技術まとめ】VR/AR/MRの解説とメタバースとの違い
参考:MR(複合現実)とは?VRやARとの違いや業界別MR導入事例を解説
この章では、XRデバイスの種類や特徴などを詳しく紹介します。
XRデバイスとは?
XRデバイスとは、VRやAR、MR、SR技術を実現するためのデバイスです。XRデバイスを活用すれば、今までに得られなかったような新しい体験ができます。
XRデバイスには、身体認識センサーや裸眼立体視ディスプレイ、自立移動デバイスなどが搭載されているため、ユーザーの動きに応じた表示や操作が可能です。また、ユーザーの動きに連動可能なため、産業や医療、教育などさまざまな分野での応用が期待されています。
XRデバイスとしては、主にVRゴーグルやMRグラスなどの種類がありますが、広義にはスマートフォンやタブレット、PCなどもXRデバイスです。
XRデバイスの種類
主なXRデバイスは以下の4種類です。
- VRヘッドセット
仮想現実の環境に没入するためのデバイスです。ユーザーは主に視覚と聴覚を通じて仮想世界を体験できます。代表的な製品としては、Oculus QuestやHTC Viveなどです。VRヘッドセットに関しては、下記の記事を参考にしてください。内部リンク:最新VRゴーグルまとめ一覧|各種特徴や性能を徹底比較! - ARグラス
現実の視界にデジタル情報を重ねて表示する拡張現実用のデバイスです。代表的な製品としては、XREAL社が開発するXLEAL Air 2 UltraやGoogle Glassなどがあります。ARグラスについての詳細は下記の記事を参考にしてください。内部リンク:最新ARグラスまとめ|各種特徴や性能を徹底比較! - MRデバイス
MRはVRとARの要素を組み合わせた技術です。MRデバイスの活用により、現実世界の物体と仮想物体が相互作用します。これにより、ユーザーはよりリアルな体験が可能です。代表的な製品には、Apple社のApple vision Pro、Microsoft社のHoloLens 2をはじめMeta社のMeta Quest 3などがあります。 - SRデバイス
SRデバイスは特定のシミュレーション環境を提供します。その力を発揮できるのは、トレーニングや教育の分野です。SRデバイスによって、ユーザーは安全な環境で実践的なスキルを学べます。
国内XRデバイスの特徴
国内のXRデバイスについて考えてみましょう。
国内XRデバイスは、VR、AR、MR技術の進化にともなって以下のような6つの特徴があります。
- 高い没入感
視野角や解像度が向上/VRデバイスは360度の視界を提供している - 軽量化
長時間の使用でも疲れにくい - スタイリッシュなデザイン
日常的に使用できるようなデザイン - インタラクティブな体験
手の動きや視線を追跡する技術が進化 - ユーザーが自然に仮想空間と対話できる
ビジネス向けの活用/デジタルツイン技術を用いたシミュレーションやトレーニングに注目 - ソフトウェアエコシステムの充実
さまざまなアプリケーションやコンテンツが提供されている
国内XRデバイスは、とくに製造業の現場で多く活用されています。3Dデータを活用したり、イメージを共有したりすることで、コスト削減や業務の効率化が可能です。
国内XRデバイスの選定ポイント
国内XRデバイスを採用するにあたり、注意しなければならないポイントは以下のとおりです。
- 用途に最適なデバイスである
- 製品本体と交換部品が安定供給されている
- 開発し易い仕組みである
- メンテナンス性が考慮されている
- アプリケーションが豊富である
使い勝手についても重要ですが、それ以上に購入後のメンテナンスに注意しましょう。メンテナンスが難しかったり、交換部品が供給されない状況では、継続利用が難しくなります。
国内XRデバイスの最新5選!人気モデルの特徴と性能を詳しく解説
国内メーカーのXRデバイスの中から厳選した5機種を紹介します。
・dynaEdge XR1(Dynabook)
・MiRZA(NTTコノキューデバイス)
・PlayStation VR2(Sony)
・MeganeX superlight 8K(Shiftall)
・InfoLinker3(桜井株式会社)
それぞれの発売時期と価格は以下のとおりです。
| XRデバイス | 発売時期 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| dynaEdge XR1 | 2025年春(発売予定) | オープン価格 |
| MiRZA | 2024年10月 | 248,000円 |
| PlayStation VR2 | 2023年2月 | 58,161円(参考価格) |
| MeganeX superlight 8K | 2025年1月~2月(発売予定) | 249,900円 |
| InfoLinker3 | 2023年2月 | 199,500円 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AIによる翻訳が可能『dynaEdge XR1』(Dynabook)
Dynabook株式会社から2025年春に発売予定になっているXRデバイスが、『dynaEdge XR1』です。分類はフルHD解像度の法人向け両眼透過型XRグラスになっています。
Dynabook株式会社は、川崎タイプライタ株式会社から東京芝浦電気(株)、東芝ビジネスマシン株式会社などを経て2019年1月にDynabook株式会社となりました。現在はシャープ株式会社の完全子会社となっています。
『dynaEdge XR1』の特筆すべき特長は、AIによる会話の字幕表示や翻訳が可能な点です。近年、AIは日進月歩の早さで進化しています。AI搭載で即座に字幕表示や翻訳ができることで、ストレスなく映像を楽しめるでしょう。
また、カメラ映像の拡大表示などの多彩な機能を備えている点にも注目です。価格はオープン価格となっているため、具体的な金額はわかりません。2025年春の発売が待ち遠しいXRグラスです。
約125gのXRデバイス『MiRZA』(NTTコノキューデバイス)
NTTコノキューデバイスが開発した『MiRZA』は、NTTグループとシャープのテクノロジーを駆使して開発されたXRデバイスです。
主なスペックは以下のとおり。
- 重量:約125g
- サイズ:
(使用時)約187mm(W)×約45mm(H)×約184mm(D)
(収納時)約187mm(W)×約45mm(H)×約96mm(D) - ディスプレイ/光学装置
解像度:FHD (1920×1080)
視野角:45°(対角)
輝度:約1,000nits
光学装置:MicroOLED 両眼フルカラー - 連続使用時間:1~1.5時間
大きな特長は約125gという重量の軽さです。長時間の使用にも苦になりません。また、世界で初めてSnapdragon® AR2 Gen1チップセット搭載し、スマートフォンとの無線接続を可能にしています。これにより、ケーブルレスで自由な操作が可能となり、AI処理能力の向上や消費電力の削減も実現しています。
さらに6DoFコンテンツ対応となっており、空間認識機能により、現実空間に3Dオブジェクトを配置することが可能です。これにより、没入感の高いXR体験を提供します。
これらの特徴により、MiRZAは日常生活やビジネスシーンでのシームレスなXR体験を可能にしてくれるでしょう。
高解像度で没入感のある体験を実現『PlayStation VR2』(Sony)
『PlayStation VR2』は『PS VR2 Sense』のコントローラーおよびステレオヘッドホンがセットのXRデバイスです。SonyがPlayStation5向けのバーチャルリアリティシステムとして開発しました。
主なスペックは以下のとおりです。
- 解像度:片目2000×2040
- フレームレート:4KHDRの映像・最大120fps
- 参考価格:58,161円(税込)
『PlayStation VR2』の特長は、高解像度で没入感のある映像が見られることや、視線トラッキングが優れている点が挙げられます。各目に2000 x 2040ピクセルの解像度を提供することで、合計で4K相当の高精細映像を実現しています。また、ゲーム内のアバターが、視線を読み取ることでユーザーの感情や反応を再現します。
また、ハプティックフィードバック、アダプティブトリガー、トラッキング、フィンガータッチ機能など、さまざまな工夫がされている点にも注目です。
超軽量VRヘッドセット『MeganeX superlight 8K』(Shiftall)
『MeganeX superlight 8K』はShiftallが開発した超軽量VRヘッドセットです。
Shiftall社は、2018年4月にパナソニックHDの子会社を経て、2024年2月に全株式がC&R社に譲渡されました。C&R社は建築やAI、DX、食、医療などさまざまな分野のグループ会社を持つ、国内を拠点とした企業です。
『MeganeX superlight 8K』のスペックは以下のとおり。
- 重量:185g未満
- 解像度:3552×3840(片目)
- SteamVRトラッキングに対応
- 価格:249,900円(税込)
『MeganeX superlight 8K』の最大の特長は、VRヘッドセットでありながら185g未満という超軽量化を実現している点です。また、解像度についてもApple Vision Pro以上となっており、ストレスなく美しい映像を楽しめます。
発売に関しては2025年1月から2月に発送開始予定となっており、今後話題になることは間違いありません。
LTE搭載の国産スマートグラス『InfoLinker3』(桜井株式会社)
桜井株式会社が開発した『InfoLinker3』は、LTE通信機能を搭載しています。LTE通信機能の搭載は業界初。LTE通信機能によって、電話回線での通信が可能となります。
詳しいスペックは以下のとおりです。
- 本体構成:ネックバンド+ヘッドマウント
- OS:Android 10.0
- ディスプレイ:μOLED(有機EL)nHD+(640×400)
- 光学モジュール:0.56型(8.0mm×12.0mm)視野角:20.2°
- カメラ:F値:1.8 / 画角:78.2°
静止画:1,200万画素
動画:4K・30fps・電子式ブレ補正機能 - 重量
ネックバンド:約380g(バッテリー込み)
ヘッドマウント:約150g - 携帯電話回線:4G / LTE対応・SIMカードスロット搭載(nanoSIM)
『InfoLinker3』の最大の特長は、LTE通信によって通信できる点です。したがって、他社製品と異なり、Wi-Fiがない環境でも通信機能が使用できます。また、防塵・防水対応のため、雨天の屋外使用も可能です。
XRデバイスの活用業界
XRデバイスは国内でもさまざまな業界で活用されています。たとえば、以下のような3つの業界です。
- 教育/訓練
VRを使用して特殊な作業現場や機器を使った研修が可能。
例:ANAのグランドハンドリング部門訓練 - 医療
ARを使用して手術支援や患者への治療説明などが可能。
例:リバビリ支援 - 警備
監視カメラや生体認証リーダーなどを用いたXRによる警備が可能。
例:花火大会の駅周辺警備
上記の例について、もう少し詳しく解説します。そのほかのXR活用事例は下記の記事を参考にしてください。
ANAがVR訓練シミュレーターを導入
ANAでは2024年10月より、VR訓練シミュレーター「∀TRAS(アトラス、ANA Training Systemの略称)」を導入し、牽引車の操縦訓練などを行っています。
グランドハンドリングでは機種ごとに資格取得が必要なため、人材不足に悩まされていました。∀TRAS導入により、人材不足を解消させるのが狙いです。
従来の育成訓練は、空港内で実機・実車を使用して実施しなければなりません。したがって、訓練のタイミングも難しく安全にも配慮が必要であり、資格取得が困難な状況でした。
一方で∀TRASを導入したことで、バーチャル上で安全に訓練が実施できます。特殊な訓練が必要な場合には、XRデバイスの活用がおすすめです。
VRを活用したリハビリのサポート
パーソナルリハビリスペースTrayR(トレイル)ではリハビリにXRデバイスを活用しています。
実際に利用しているサービスは、mediVR社が提供するリハビリサポートサービス『mediVRカグラ』。『mediVRカグラ』は腕や足などのリハビリに最適なシステムです。
TrayRでは歩行が困難な人向けのリハビリでは、考えながら体を動かさなければなりません。そこで、XRデバイスを使用し、歩行に必要な運動機能や姿勢バランス、認知機能などを総合的に評価しています。
脳卒中や運動機能障がい、認知機能障害など幅広い対象の機能回復が目的です。
InfoLinker3を警備業務に活用
警備業界も多分に漏れず慢性的な人材不足が大きな課題です。また、教育時間の不足も指摘されています。とくに大きな行事が開催されるときの警備では、効率よく確実に警備しなければなりません。
株式会社エース警備保障では、花火大会の警備依頼がありました。ニュースでも取り上げられることが多いのが、花火終了後における駅周辺の混雑です。
エース警備保障では、XRデバイス『InfoLinker3』を活用し、本部で目視できないエリアの状況を画像と⾳声によって遠隔で確認しました。
使用したのは、親機のノートPCと6台の『InfoLinker3』です。『InfoLinker3』は各警備区の責任者及び担当者が実装しました。本部において画像や音声の確認ができるため、経験の浅い警備員にも詳細指示が可能な点が大きなメリットです。
まとめ〜国内のXRデバイスでビジネスを加速〜
本記事は国内のXRデバイスについて、種類や特徴、ビジネスへの活用事例などを詳しく紹介しました。
国内のXRデバイスは種類が少ない印象があるかもしれませんが、実際は多くの企業が商品化しています。しかも、技術レベルは海外メーカーと比較しても遜色ありません。
ぜひ、記事内で紹介した活用事例を参考に、国内XRデバイスをビジネスに活用してみてください。人手不足やコスト削減、技術継承などの大きな課題についても、解決の糸口となるでしょう。
昨今は国内メーカーのXR技術は向上し、目標の80%程度のところまで到達しているといわれています。今後は技術の向上とともに、XR周りの環境も整備されることは間違いありません。