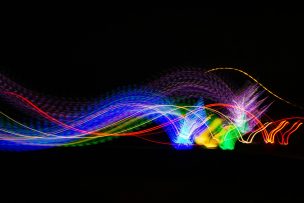
企業のIT活用における姿勢や取り組みを、「攻めのIT」や「守りのIT」と呼ぶことがあります。
業務の効率化やセキュリティ強化を目的とする「守りのIT」に対し、「攻めのIT」はビジネスの成長や競争力の向上を目指すものです。
この姿勢の違いは、具体的にはIT投資対象の違いとなり、企業競争力に大きく影響していきます。
本記事では、攻めと守りのITのそれぞれの違いを解説し、DXを推進する上で重点を置くべきと考えられている「攻めのIT」を取り入れるための4つのステップを紹介します。
<目次>
攻めのITとは?——成長戦略を加速させる攻めのIT活用
「攻めのIT」とは、企業が売上拡大や新規事業の創出、顧客体験の向上など、ビジネスの成長を目的としてITを戦略的に活用することを指します。単なる業務効率化ではなく、市場での競争優位を築くための“攻めの一手”としてITを位置づけるのが特徴です。
攻めのITの具体例
攻めのITは、自社の成長戦略をITでどのように後押しできるかを考えることから始まります。ここでは、企業が実際に行っている「攻めのIT」施策の中から、単なるデジタル化にとどまらず、事業の拡大や新たな収益機会の創出に直結するものをピックアップして紹介します。
- パーソナライズドマーケティングの自動化
顧客データをAIで分析し、購買履歴や閲覧傾向に応じて最適な商品提案を自動で実施。コンバージョン率の向上と顧客満足度の強化につながります。 - 新規事業立ち上げにおけるAIの活用
新サービスの企画段階からAIを用いた市場分析・需要予測を行うことで、リスクを抑えつつ確度の高い事業展開が実現できます。 - 海外市場向けの多言語対応Webサービス
グローバル展開を見据えたWebサイトやECサイトの多言語化、現地ニーズに即したカスタマイズなど、新市場へのスムーズな参入を支えます。 - サブスクリプション型ビジネスへの転換支援
従来の一括販売型から、定額制のサブスクリプションモデルへ移行。専用の課金管理システムを導入し、継続的な収益基盤を構築します。 - マーケティングオートメーション(MA)による商談創出
見込み顧客の行動履歴をもとに、ナーチャリングを自動で行い、営業組織へホットリードを提供。営業効率と成約率の向上が見込めます。
これらの施策は、すべて「企業の成長を支えるIT活用」であり、まさに“攻めのIT”の具体例です。ただし、成果が短期間では見えにくい場合もあり、一定のリスク許容と中長期的な視野が求められます。
守りのITとは?——安定運用とリスク管理を支えるIT活用
「守りのIT」とは、企業活動を安定的に継続させることを目的としたIT活用のことです。サイバー攻撃やシステム障害、自然災害など、ビジネスを脅かすリスクに備える施策のほか、法令遵守や業務の効率化といった“足元の強化”に焦点を当てます。
攻めのITが「事業拡大や売上向上のためのIT投資」であるのに対し、守りのITは「リスク最小化と安定運用のためのIT整備」に位置づけられます。企業としての信頼性を保つためにも、守りのITは欠かせない基盤です。
守りのITの具体例
守りのITは、一見すると地味な取り組みに見えるかもしれませんが、企業の事業継続や信頼性の確保には不可欠な存在です。ここでは、日常業務の安定運用やリスク対策を目的とした「守りのIT」の代表的な施策を紹介します。どれも、企業活動の基盤を支えるために重要な役割を果たしています。
- クラウド環境によるシステムの安定運用
オンプレミスに比べて、サーバー管理や保守の負担・コストを軽減でき、柔軟でスケーラブルな運用が可能になります。障害時も迅速な復旧ができるため、安定稼働とBCP対策の両立に効果的です。 - セキュリティ対策の強化(ウイルス対策・ファイアウォール等)
外部からの攻撃や内部不正を防ぐために、セキュリティソフトやアクセス制御を徹底し、情報資産の保護を図ります。 - データバックアップと災害対策の整備
定期的なバックアップ運用や災害時の復旧フロー整備により、万が一のトラブル時でも迅速なリカバリーが可能になります。 - ERP(基幹業務システム)による業務の効率化と統制強化
人事・経理・在庫管理などの業務プロセスを一元管理することで、作業ミスや重複作業を削減し、業務の信頼性と生産性を向上。結果として、人的リソースや運用コストの削減にもつながります。 - 法令遵守・コンプライアンス対応のためのシステム整備
電子帳簿保存法や個人情報保護法などに対応するためのシステム導入により、法的リスクを回避し、企業の信頼を確保します。
これらの「守りのIT」は、直接的な売上増加こそ目的ではないものの、業務の効率化やインフラ最適化によるコスト削減効果をもたらし、企業経営の健全化に大きく貢献します。また、突発的なリスクから事業を守り、長期的な信頼と安定を築くためにも、計画的かつ戦略的な整備が不可欠です。
攻めのITと守りのITの違い
ここまで紹介したように、「攻めのIT」と「守りのIT」は、目的や投資領域、成果の現れ方が大きく異なります。どちらが優れているというものではなく、企業の成長フェーズや経営課題に応じてバランスよく活用することが重要です。
以下の表では、それぞれのIT活用の違いを整理しています。
| 項目 | 攻めのIT | 守りのIT |
| 目的 | 売上拡大、新規事業の創出、競争力強化 | 安定運用、リスク回避、コスト削減 |
| 主な施策 | マーケティング強化、DX推進、新サービス開発 | セキュリティ対策、業務システムの維持管理、法令遵守 |
| 投資対象 | 顧客向けサービス、新技術の導入 | 基幹システム、インフラ整備、運用基盤 |
| 成果の性質 | 中長期的な成長に寄与、成果が不確実な場合もある | 即効性は低いが、安定性・信頼性の向上に直結 |
| リスク特性 | 実成果が出るまで時間がかかる、投資失敗の可能性あり | 投資対効果が見えにくい、対策を怠ると被害が大きくなる |
「攻め」と「守り」は対立するものではなく、両輪として戦略的に組み合わせることが、持続的な成長と安定を実現する鍵となります。
「攻めのIT」DX推進に必要なポイント
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえで、「守りのIT」だけでなく「攻めのIT」も意識してみましょう。単なる業務効率化にとどまらず、新しい価値を生み出し、競争力を高めるために必要なポイントを解説します。
DX推進を行うなら攻めを意識する
DXの本質は、単なるIT導入や業務のデジタル化ではなく、企業の競争力を高めることです。従来の「守りのIT」だけでなく、売上向上や新たな事業創出につながる「攻めのIT」を意識してください。例えば、AIやビッグデータを活用したマーケティングの最適化、ECサイトの強化、サブスクリプション型のサービス提供など、デジタル技術を駆使して新たな価値を創造することが求められます。
海外企業に対抗するために攻める
グローバル市場では、デジタル技術を活用した革新的な企業が次々と登場しています。GAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)をはじめとする海外企業は、DXを推進することで圧倒的な競争力を持っています。日本企業が海外勢に対抗するためには、現状維持ではなく、デジタル技術を積極的に活用し、新しいビジネスモデルを生み出す「攻めのIT」が不可欠です。クラウドやAI、IoTなどの最先端技術を取り入れ、ビジネスの可能性を広げてみましょう。
「2025年の壁」を打破するために攻める
経済産業省が提唱する「2025年の壁」とは、既存の古いITシステムを放置したままだと、2025年以降に大きな損失が発生するという課題を指します。老朽化したシステムの維持や管理に多くのコストがかかり、DXの推進が遅れるリスクがあります。打破するためには、古いシステムを見直し、最新のデジタル技術を積極的に導入しましょう。クラウド化や最新技術への移行を進めることで、企業の柔軟性を高め、変化に対応できる体制を整えてください。
DX人材の活用
DXを推進するためには、適切な人材を確保し、育成することが必要です。
- 社内人材の育成
- 外部人材の活用
- ITとビジネスの融合
- チーム体制の構築
DXを推進するには、社内外の人材を効果的に活用してみましょう。まず、社内の人材を育成し、デジタル技術の活用スキルを身につけさせます。外部の専門家を採用することで、最新の知識や技術を取り入れ、スキル不足を補います。さらに、ITとビジネスの融合を進め、両者を理解できる人材が必要です。強力なチーム体制を構築し、メンバーが協力し合える環境を整えることが成功へのカギとなります。
攻めのITへの投資額を増やす
DXを成功させるためには、ITへの投資が不可欠です。しかし、日本企業の多くは「守りのIT」に偏りがちで、攻めのITへの投資が不足しています。例えば、海外企業では売上の10%以上をIT投資に回すケースもありますが、日本企業は数%程度にとどまることが多いです。競争力を高めるためには、デジタル技術に積極的に投資し、新たな価値を生み出すことが必要です。
攻めのIT導入の4つのステップ
攻めのITを導入することは、業務の効率化や企業の競争力を向上させます。「攻めのIT」を成功させるには、導入前の準備とその後の改善が欠かせません。ここでは、攻めのIT導入の4つのステップを紹介し、業務をどのように変えて、企業の競争力をどう強化するかを解説します。
1.導入前は各部署との連携が必須各部署との連携で現場ニーズを明確にする
攻めのITを導入する際、経営層やIT部門だけで方針を決めてしまうと、現場の実態と乖離したシステムになり、定着しないリスクがあります。そのため、導入前から各部署と連携し、業務フローや課題、改善ニーズを現場視点で把握することが重要です。連携を通じて現場の声を反映することで、導入するITが実用的かつ効果的になり、運用後のトラブルや利用定着の遅れも防げます。また、部署間の協力体制が早期に構築されることで、全社的な推進力にもつながります。
2.ITツールでコミュニケーションと業務をデジタル化する
業務の連絡手段を、ITツールに切り替えることにより、情報伝達の効率が良くなります。メールやチャットツールに切り替えることで、リアルタイムで情報を共有でき、即時性が向上します。業務で使う資料やデータもWordやExcel、PowerPointを活用することで、手作業でのミスを減らし、業務のスピードを大幅に向上させることが可能です。ITツールを導入することにより、従来の方法に比べて、業務全体の生産性が大きく向上し、コミュニケーションの質も改善されます。
3.業務の自動化とAI活用でさらなる効率化を図る
ITツールの導入後、さらに効率化を進めるためには、業務の自動化やAIツールを活用することが効果的です。例えば、定型業務を自動化することで、社員の負担を軽減し、時間をより価値のある業務にあてることができます。また、AIや機械学習を活用することで、データ分析や顧客対応の精度を高め、業務の品質向上にもつなげることが可能です。企業は自社の業務フローに合ったシステムを開発・運用することで、製品や成果物の品質が向上します。
4.競争力を強化していく
ITを活用して、業務基盤をしっかりと固めた後に目指すのは「競争力の強化」です。このステップでは、売上向上や新規顧客の獲得を目指して、ITをさらに積極的に活用します。新しい技術やツールを積極的に導入し、業界内での競争優位性を確立するための基盤を作り上げます。ITを用いて顧客への価値提供を変革し、競争力を強化していくことで、より柔軟に市場の変化に対応できる企業へと進化していくのです。
「攻めのIT活用指針」を活用する
4つのステップを進めるために、参考にしたいのが「攻めのIT活用指針」です。この指針では、IT導入における具体的な戦略や手法が紹介されており、企業がITをうまく活用するためのポイントが示されています。詳細は以下のリンクで確認できます。
この指針を参考にしながら、自社に合うIT活用方法を導き出し、業務の革新を進めていくことをおすすめします。
「攻めのIT」に遅れる日本の状況
「攻めのIT」の導入が進む中で、日本企業はその変革に遅れを取っているという現状があります。ここでは、デジタル化の波に乗り遅れないためには、どのような課題があるのか、解決策は何かについて解説します。
デジタル化の遅れへの懸念
デジタル化の遅れに対する懸念は年々強まっています。調査によると、欧米に比べて遅れを感じる企業は8割に達し、その多くが「影響がある」と答えています。このため、多くの企業がデジタル戦略を立て、実行に移し始めています。特に「人材」の重要性が高まり、顧客接点の多い業界では対面営業や接客力も重視されています。デジタル化の遅れを取り戻すためには、攻めのIT戦略の実行が欠かせません。
攻めのITへの今後の課題
攻めのITを進める企業は、顧客満足度向上を最優先課題として、新しい事業モデルや革新的な価値提供が求められています。しかし、実際に進展している企業は少なく、多くはデジタル化の成果を実感していません。攻めのITを効果的に活用するには、柔軟に変化に対応し、新技術を取り入れて競争力を維持することが重要です。特にサービス業や製造業、金融業などでは、デジタル化に適応しなければ競争で遅れるリスクがあります。成果を上げるには、適切な人材とリソース、強いリーダーシップが必要です。
他者との連携の遅れ
攻めのITを進める企業にとって、他社との連携は重要ですが、連携の遅れが課題となっています。約40%の企業が連携を進め、9割以上がその重要性を認識しています。特にトップランナーは、他業界の企業やTechベンチャー、研究機関との連携を強化しています。一方、セカンドランナーやフォロワーは、ITベンダーやSIerとの連携に依存しています。デジタル化を進めるには、連携先を慎重に選び、戦略的に協力関係を築くことが大切です。また、デジタル化は小さく始め、トライ&エラーで効果を上げることが推奨されています。
攻めのITを推進するための組織連携と企画力
攻めのITを成功させるためには、事業部門とIT部門が共同で企画・実行することが重要です。2017年以降、デジタル化が進み、IT部門がその役割を担う割合が増えています。成果を上げている企業は、両部門が連携したチームで進めており、デジタル化専門部門もその役割を強化中です。現在、企業の多くはデジタル化に2割以下の予算を投資しています。将来的には半数以上が「攻めのIT投資」を行う見込みです。特にトップランナー企業は、IoTやAI、RPAに投資し、PoCを通じて効果を確認した後に本格的な投資を行っています。
攻めのITに必要な人材
「攻めのIT」を推進する上で鍵を握るのは、テクノロジーの知識や技術力だけでなく、ビジネスを前に進める力を持った人材です。特に注目すべきは、以下の3つの資質です。
- 事業企画力:市場や顧客ニーズを捉え、ITを活用して新たなビジネスを構想・設計する力
- 改革推進力:現場の抵抗や不確実性を乗り越え、組織を動かして変革を実行する力
- リーダーシップ:リスクを取ってチャレンジを支援し、関係者を巻き込んで成果に導く力
こうした力を持つ人材は、IT部門だけに必要なのではなく、むしろ事業部門とIT部門を連携する“橋渡し役”として重要です。例えば「デジタル企画担当」「プロダクトマネージャー」「データアナリスト」などのポジションを定義し、役割に応じた育成・配置が求められます。また、自社内で人材を育成しつつ、外部の専門人材やパートナー企業と連携するハイブリッド型のアプローチも効果的です。デジタル戦略の成否は、最終的には「誰が動かすか」にかかっていると言っても過言ではありません。
「攻めのIT」4つの成功事例
デジタル化を積極的に進める「攻めのIT」を実践し、成功を収めた企業の事例を見てみましょう。各業界でのデジタル活用方法や取り組みを紹介します。
機械メーカー
老舗の某建築機械メーカーは、建設機械とIoTデータを活用し、人手不足や高齢化問題を解決するシステムを開発しました。自動化で目視作業や作業員の人数を最適化し、オペレーションの負担を減らしたのです。AIとIoTで機械の稼働状況を監視し、予防保全を行ってダウンタイムを削減します。データ解析で製品設計を最適化し、品質向上とコスト削減を実現しました。
食品メーカー
某食品メーカーは、AIを使って商品のパッケージデザインを自動生成するシステムを開発し、トレンドを反映した独創的なデザインを提供しています。このシステムは売り場の活性化にも貢献しました。また、VR技術で商品パッケージ案を売り場に再現し、顧客視点を重視した商品開発を強化しています。
IT企業
某IT企業では、リモートデスクトップやWindowsリモートアシスタンスを活用し、リモート勤務を実現しました。クラウドサービスを通じて、小売・金融・医療・行政など多くの業界に価値を提供し、セキュリティサポートや柔軟なストレージサービスを提供しています。AI技術やクラウドを活かして顧客の業務効率化を支援し、内部業務の迅速化とコスト削減を実現しています。
製薬会社
製薬業界は、ITを活用して研究開発の効率化を進めています。特に、AIを用いて薬剤の候補を探索し、ビッグデータを活用して臨床試験のデザインを最適化しています。これにより、新薬の開発スピードを加速させ、医薬品市場での競争力を強化しました。さらに、IoT技術を活用して製造ラインの品質をリアルタイムで監視・管理し、品質の一貫性を確保しています。
アパレル業
某大手アパレルメーカーは、スマホアプリに買い物アシスタントサービスを導入し、オンラインとオフラインを統合したショッピング体験を提供しています。AIを活用して商品検索やコーディネート提案、サイズ選びをサポートし、顧客データを基にマーケティング戦略を強化しました。また、オムニチャネルを推進し、RFIDタグによる無人レジで待ち時間を削減に取り組みます。AIによる需要予測で在庫を減らし、サプライチェーンのデジタル化で生産・配送効率を向上させています。
まとめ
企業は「攻めのIT」を活用して競争力を高め、未来の成長を支える戦略的なアプローチを取っています。守りのITが安定性とセキュリティを重視するのに対し、攻めのITは市場に新たな価値を提供し、変化に柔軟に対応することが目的です。企業は戦略的な計画を立て、今後の成長を実現するため、攻めのITを積極的に活用していきます。












