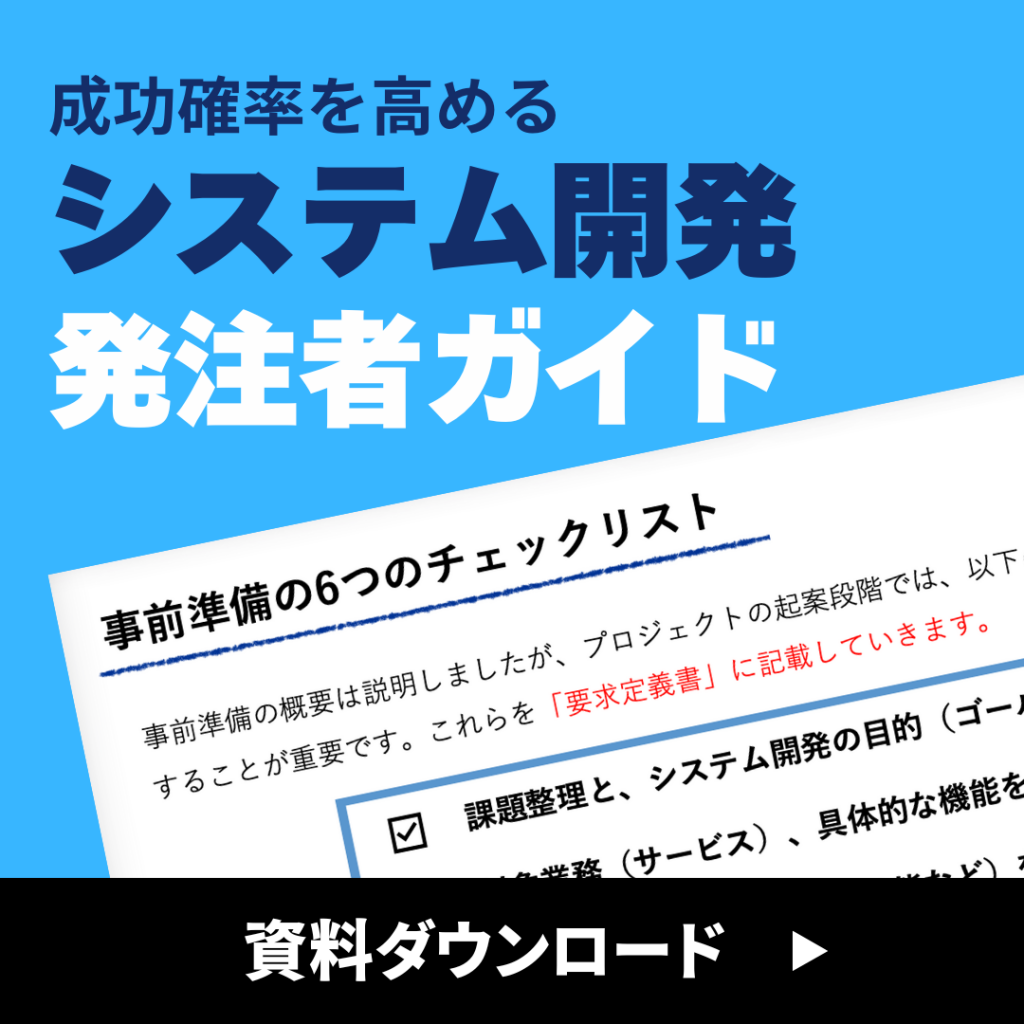新しい顧客体験を創造したいものの、従来のマーケティング手法では限界を感じていませんか。
熱狂的なファンを起点にしたビジネスモデルに関心はあっても、具体的な推進方法や社内を説得するためのデータが不足している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、約3兆5,000億円規模に成長した推し活マーケティングの全貌を解説します。消費者行動のデータ分析から、コミュニティ設計やパーソナライズといったデジタル施策、成功事例まで網羅的に紹介します。
新規事業創出や顧客エンゲージメント向上に悩む方にとって、実践的な道筋を示す一助となれば幸いです。
<目次>
推し活に見る消費者の新しい行動様式
・「推し消費」の心理と「体験型」消費の拡大
・SNSを起点とする情報収集と拡散
推し活マーケティングのデジタル戦略
・コミュニティを起点としたエンゲージメント強化
・データを活用したパーソナライズとコンテンツ提供
・企画から実行までを迅速に行うアジャイルな体制
推し活マーケティングとは
「推し活マーケティング」とは、消費者が「推し」と称するアイドルやキャラクターを熱心に応援する「推し活」という行動に着目し、購買やブランドロイヤリティの向上につなげるマーケティング手法です。
推しの対象は非常に幅広く、アイドルやキャラクターだけでなく、日常使いの美容品やサービスなども含まれます。
なぜ推し活がマーケティングとして重要なのかを説明します。
推し活マーケティングが注目される背景
推し活マーケティングが今、多くの企業から注目を集めています。その理由は、推し活が単なる趣味の枠を超え、約3兆5,000億円規模の巨大な経済圏を形成しているためです。
この市場を支えるのは1,384万人にのぼる推し活人口であり、一人あたりの年間平均支出額は25万円を超えています。
さらに注目すべきは、推しとのコラボをきっかけに企業やブランドに好感を持った人が79.2%に上るという調査結果です。このような消費者の熱量と経済的インパクトが、推し活マーケティングを新たな顧客接点の手段として企業に重要視させています。
参考:【推し活男女に調査!】79.2%が、推しとのコラボがきっかけで「企業やブランドに好感を持ったことがある」
推し活に見る消費者の新しい行動様式
推し活を楽しむ人々の行動は、従来の消費スタイルとは大きく異なります。単にグッズを購入するだけでなく、体験や感情を重視した消費へと変化しています。
また、SNSを活用した情報収集と拡散が、この新しい消費行動を後押ししているのです。
ここでは、推し活における消費者の心理と、デジタル時代ならではの行動パターンを詳しく見ていきましょう。
「推し消費」の心理と「体験型」消費の拡大
推し活における消費行動は、6つの心理によって支えられています。「共有」「応援」「つながり」「憧憬」「探求」「所有」という心理が相互に作用し、熱量の高い消費を生み出しているのです。
実際に、推し活を楽しむ人は可処分所得の約37.4%※を推し活支出に充てており、その行動は趣味の範囲を超えています。
注目すべきは、消費の対象がモノからコトへ拡大している点です。遠征や公式グッズ、オンライン配信といった複数のカテゴリで支出が発生しており、過去1年間では全カテゴリで8割以上の人が支出を増やしています。
推しとの体験を求める消費者の姿勢が、新たな市場機会を生み出しているのです。
SNSを起点とする情報収集と拡散
SNSは推し活における情報収集と拡散の中心的な役割を担っています。推し活を楽しむ人々は、新曲リリースやイベント情報をまずSNSで入手し、ファン同士の会話から追加情報を得ることが一般化しました。
さらに、「このグッズを買った」「イベントに行った」といった投稿が口コミとして拡散し、フォロワーへ広がっていきます。こうしたSNS上での共感や同時体験は、消費意欲を刺激する重要なきっかけとなるのです。加えて、リアルイベントでの体験をSNSコンテンツ化する動きも活発化しており、特に、デジタル施策とリアル体験を連動させる設計力が求められています。
推し活マーケティングのデジタル戦略
推し活マーケティングを成功させるには、デジタル技術を活用した戦略的アプローチが欠かせません。具体的には、ファンとの関係性を深めるコミュニティ設計、一人ひとりに合わせた情報提供、そして変化の速い市場に対応できる開発体制が重要です。
ここでは、企業が実践すべき3つのデジタル施策について解説します。
コミュニティを起点としたエンゲージメント強化
ファンコミュニティは、推し活マーケティングにおける最も重要な資産となります。ファン同士が交流できる場を設けることで、愛着や居場所感が生まれ、ブランドへのロイヤリティが高まるためです。
具体的には、SNSクローズドグループやDiscordなどを活用したオンライン空間と、ファンミーティングのようなオフライン施策を組み合わせる設計が効果的です。
さらに、限定情報や先行体験をコミュニティメンバー向けに提供することで、特別感を演出できます。ハッシュタグキャンペーンといったファン参加型の企画も、コミュニティ内での相互作用を促進し、UGCを生み出すきっかけになるのです。
ただし、過度な商用誘導は反感を招くため、ファンへの配慮とバランスを保つ姿勢が求められます。
データを活用したパーソナライズとコンテンツ提供
一人ひとりのファンに最適な体験を届けるには、データ基盤の構築が不可欠です。
会員情報、購買履歴、閲覧履歴、イベント参加履歴などを統合し、ファンの熱量や属性に応じてセグメント分類を行います。その上で、ライト層とコア層で接触頻度や提案内容を変えるなど、きめ細やかな対応が可能になります。
たとえば、好みのテーマや行動履歴に即したコンテンツをメールやアプリ通知で配信し、ABテストを通じて効果を検証していく手法が有効です。
ただし、データ活用には注意も必要です。過度なパーソナライズは「監視されている」という不快感を与えかねません。個人情報保護法への準拠はもちろん、ファンが安心できる「気遣い感」を持たせた設計が大切です。
企画から実行までを迅速に行うアジャイルな体制
推し活市場は変化が激しく、スピード感のある対応が成功の鍵を握ります。
そのため、アジャイル開発の考え方を取り入れた体制づくりが重要です。仮説を立て、最小限の機能で実装し、検証と改修のサイクルを高速で回していきます。
まずはミニ企画や限定版施策といった小さな試みから始め、ユーザーフィードバックをすぐに反映させる運用が効果的です。
また、開発者、マーケター、データ分析担当、デザイナーが混成で動くクロスファンクショナルチームを編成することで、迅速な意思決定を実現できます。
限定性や希少性を活かした施策はタイミングが命であり、企画から実行までのリードタイムを短縮できる体制が、競合との差別化につながるのです。
推し活マーケティングの成功事例
推し活マーケティングの理論を理解しても、実際にどう展開すればよいか迷う担当者は少なくありません。
ここでは、デジタル技術を駆使して成果を上げた3つの事例を紹介します。
地方創生、伝統産業の刷新、BtoBサービスという異なる領域で、それぞれがDXの力を活用しながら推し活マーケティングを成功させた事例を紹介します。
地方創生に貢献するデジタル施策(JR東海)
JR東海は、アニメ作品のIPを活用した地域振興においてデジタルとリアルを融合させた施策で成果を上げています。「沼津ゲキ推しキャンペーン2025」では、JR沼津駅を起点にモバイルクイズや限定スマホ壁紙の配布を実施しました。
さらに、商店街でのシールラリーを通じて街歩きを促進し、ファンを観光目的地へと誘導する仕組みを構築しています。その結果、ライブイベント参加者だけでなく、街そのものを「推し目的地」として訪れるファンが増加しました。
スマホ壁紙やノベルティといったSNS発信を促す仕掛けも効果的で、オンライン上での拡散が来訪者増加につながっています。
地域経済の活性化とファンの満足度向上を両立させた事例といえるでしょう。
参考:JR東海「推し旅」×「ラブライブ!サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025!
伝統産業のブランド刷新(フェリシモ×池利)
通販企業フェリシモと奈良の老舗そうめんメーカー池利のコラボレーションは、ファン参加型の商品開発という新しいアプローチを示しました。フェリシモのオタ活部「OSYAIRO」が展開した「推し色そうめん」では、SNSフォロワーと一緒に商品の色を選ぶ企画を実施しています。
この共創型の設計により、発売前からファンの関心を集め、心理的な所有感を高めることに成功しました。
伝統産業である老舗そうめん企業にとって、若年層への訴求は大きな課題です。しかし、推し活という文化と結びつけることで、堅実なイメージから脱却し、ライフスタイル商品としての新たなポジションを確立できたのです。
オンライン投票やSNS連動、EC販売といったデジタル施策が、伝統産業のブランド刷新の鍵となった事例といえます。
参考:日本の夏の風物詩「そうめん」が推し色になって登場、奈良・三輪そうめんの老舗「池利」とオタ活部「OSYAIRO」のコラボレーション
AIを活用した新たな推し活サービスも(テラバース)
インフルエンサーやタレントの「AI分身」を公式LINE上で提供する、新しいファン対応サービス「Twinny(トゥイニー)」がリリースされました。
このサービスは、ファンが「推し」のAIと自然に対話できる体験を可能にし、「推し活」の新たな可能性を広げるものとして注目されています。
「Twinny」のAIは、対象となるタレント本人の口調、性格、感情を忠実に再現。 これにより、ファンからのダイレクトメッセージや質問に対して、24時間365日、いつでも「本人らしい」対応ができるようになります。
参考:DM返信もイベント誘導もAIにおまかせ!インフルエンサー分身AI「Twinny」誕生
まとめ
推し活マーケティングの戦略とデジタル施策について解説してきました。
本記事で最も重要なポイントは、推し活マーケティングの本質が熱狂的なファンの行動データから顧客の本質的なニーズを捉え、素早くデジタル施策に反映させることにあるという点です。
コミュニティ設計、データ活用、アジャイル体制という3つの要素を組み合わせることで、ファンとの深い関係性を築けます。さらに、企業のの事例が示すように、業種や規模を問わず展開可能な手法です。
この考え方は、これからの企業がDXを推進し、新しい顧客体験を創出する上で不可欠な視点となるでしょう。まずは小さな施策から取り組み、ファンの声に耳を傾けながら改善を重ねてみてください。