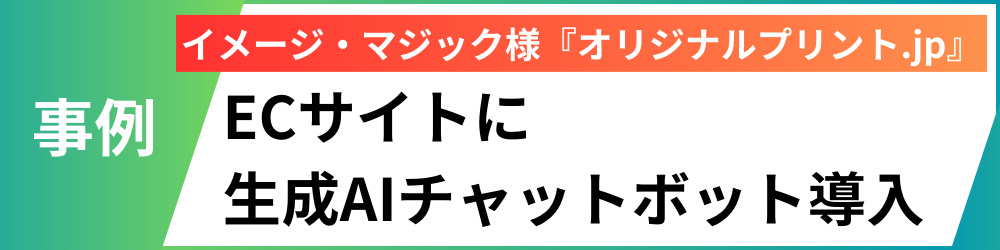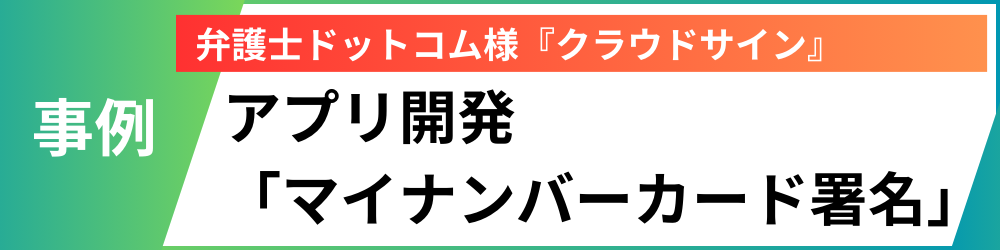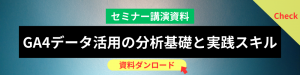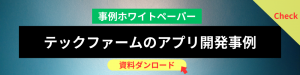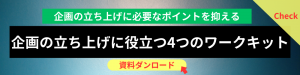生成AIに興味はあるものの、回答に対する信頼度が足りず、導入のハードルの高さを感じている人は多いのではないでしょうか。
ChatGPTとは?今さら聞けない仕組みや機能を解説
ChatGPTは2022年11月にアメリカのOpenAI社より発表されました。まだ新しいサービスではありますが、ChatGPTが世に出たことで生成AIは一気に身近なものになったと言えるでしょう。実際ChatGPTをビジネス活用している企業や人は多いでしょう。
Geminiとは?Googleの生成AIサービス基本解説
Googleの生成AIサービス「Bard」が2024年2月に「Gemini」に改名し、ChatGPTに並んで注目されています。
NeRFとは?仕組みや効果的な活用例をとともに解説
昨今ECサイトでは3D画像を挿入し、よりリアリティーのある商品の理解ができるサイトが増えてきています。これにより新たな顧客体験の向上が期待でき、返品率の低減にも繋がる可能性もあります。
【GPU基礎解説】CPUとの違い、AI開発に重要な理由とは?
生成AIが台頭している今、生成AIに関連して「GPU」や「NVIDIA」というキーワードを目にすることも増えてきました。
AI開発には膨大なデータを高速処理をする必要があり、その役割を担う装置が「GPU」です。
大規模言語モデル(LLM)とは?仕組みやビジネス活用領域を解説
大規模言語モデル、通称「LLM」を耳にしたことはありますでしょうか?
大規模言語モデルとは、自然言語処理の技術を利用して人間の言語を理解させることにより、さまざまな生成ができるAIモデルです。
バーチャルオフィス導入事例8選〜コニュニケーション不足は解消されるのか?〜
近年コロナ禍を機に、働き方の一つとしてバーチャルオフィスを導入する企業が年々増加しています。昨今ではテレワークを導入した企業も多いですが、コミュニケーション不足や人材育成しづらい環境を解決することが課題となっています。
フォトグラメトリとは?作成方法とメジャーなソフト9選
近年、ARやVRなどで3Dの画像データを見る機会が増えました。
3Dデータと触れ合う機会が増え、注目されている技術があります。それがフォトグラメトリです。
商品企画・開発やコンテンツ制作に生成AIを活用している企業事例10選
生成AIの拡大はここ数年で急激に伸びていて、商品企画・開発やコンテンツ制作などのマーケティング活動に生成AIを活用している企業が増えてきています。
【CES 2024レポート】展示製品・日本企業の傾向とCES参加ベテランの正直な感想
2024年1月9日〜12日にラスベガスにて開催された、世界最大のテクノロジー見本市「CES 2024」。
今年は4,300社以上の出展、250以上のセッションが行われ、来場者は135,000人以上となり、大盛況に終わりました。(参考:CES 2024: The Global Platform Defining Our Future)
【2024年技術トレンド】テックファーム技術顧問の注目技術
2023年はOpenAIやMicrosoftが、生成AI関連の企業向けサービスをリリースし、生成AIをはじめとする技術に多くの注目を浴びた年でした。実際の業務にどのように活用できるか情報収集を行った企業も多いことでしょう。
【2024年前半開催】先端技術・DX関連の展示会まとめ
2023年も残りわずかとなりました。
今年は特に生成AIをはじめとする先端技術に、多くの注目が集まった年でした。しかし自社のサービスにどう活かせるかわからない方も多いのではないでしょうか。
テーマに合わせた展示会に足を運ぶことで、実際に検討するサービスのデモを見ることができたり、企業に直接話を聞けたりと、有効に活用することができます。
ChatGPTでエンジニアリングはどのように変化する?
2022年11月に公開されたChatGPTは、公開わずかでありながら利用者が急増し、すでに多くの企業でビジネスへ活用されています。
ChatGPTは、プログラミングの生成ができることなど、エンジニアリングへの活用も幅広く、今後多くのエンジニアリングの場面でも活用が期待されています。
SX(サスティナビリティ・トランスフォーメーション)とは?重要性・取り組み事例を紹介
昨今はとかくSDGsへの取り組みが注目されています。
企業活動においても、国際社会におけるサステナビリティへの取り組みが必須となってきました。また、サステナビリティへの関心が高まるにつれ、「SX」への注目も高まってきています。
生成AIにおける企業の取り組み8選
多くの企業で生成AIによる取り組みが進んでいます。業務効率を目的とした、単純作業を自動化することだけでなく、よりクリエイティブなコンテンツ制作等の領域まで自動化されてきています。
Copilot for Microsoft 365とは?仕組みや特長を解説
Microsoft社から、OpenAIのGPT-4をベースとした「Copilot for Microsoft 365」のサービスが提供開始され、注目を浴びています。このサービスにより、多くの人が業務で利用しているExcelやPowerPointなどのMicrosoft 365製品で、時間短縮や生産性向上が期待されています。
RPAとAIはどう違うのか?活用例とともに解説
昨今ChatGPTなど、AIによる技術進歩が注目を集めていますが、実際にRPAとどう違うのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
ChatGPTの新機能「Advanced data analysis」の活用方法とは?
ChatGPTの新機能「Code Interpreter」が2023年7月に公開され、その年の8月に「Advanced data analysis」へと名称が変わりました。
プロンプトエンジニアリングとは?効果的な設計ポイントと必要スキル
AIによってビジネス課題を解決する事例が増えていて、今後はますますAIが多くの課題を解決するようになるでしょう。
そして、AIから正しい出力を得るのに必要なのがプロンプトです。
WebAssemblyとは?高速実行する最新技術のできる・できないこと、活用事例
今のインターネットではWebブラウザ上での情報収集だけでなく映像や音楽、ゲームなどのコンテンツを楽しめるようになりました。
そんな中、注目を集めている技術がWebAssemblyです。